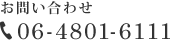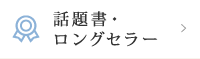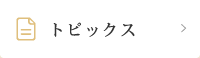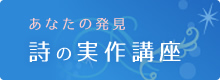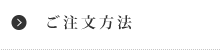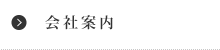![]()
194号 平和
194号 平和
- よこがお 磯 純子
- 青い空 はたちよしこ
- 小さな時間 はたちよしこ
- エルゴレア アルジェリア・サハラのオアシスにて 下前幸一
- 夏の日の午後 左子真由美
- 神々が生きてある場所 葉陶紅子
- 裸線に棲む鳥 葉陶紅子
- 鳥 升田尚世
- 散歩道 加納由将
- 業平忌 加藤廣行
- しらすじゃない 白井ひかる
- 少年の夏 斗沢テルオ
- あかいふく 吉田定一
- 洗濯物を干す 関 中子
- 黄金色の時、黄金色の日 佐倉圭史
- 知らない自分を 西田 純
- ザルツブルグの鐘の音 水崎野里子
- <PHOTO POEM>ステージ 中島(あたるしま)省吾
- <PHOTO POEM>交わらない糸 長谷部圭子
- 指 平野鈴子
- 抱きしめて 平野鈴子
- 沈黙 川本多紀夫
- 無常観 中島(あたるしま)省吾
- 人生の旅 中島(あたるしま)省吾
- 菜の花 弘津 亨
よこがお 磯 純子
あなたの横顔
ギリシャ神話の彫刻みたい
どこからも光の入ってこない
暗い部屋の中で
鼻筋のふちどりも
二重瞼(ふたえまぶた)も
淡く白く浮かびあがっていたから
誰からも呼び出されない
二人きりの部屋の中で
ゼウスも
白鳥も白牛も白百合も
大理石のしじまに封じ込まれていた
あなたと私
ギリシャ悲劇の役者みたい
どこにも観客のいない
狭い舞台の上で
粗筋もだんどりも
二重奏(デュエット)も
潔(いさぎよ)く無垢に演じつくしていたから
誰にも記憶されない
二人きりの緞帳(どんちょう)の奥で
アクロポリスの丘も
ミケーネの遺跡も
大法螺(おおぼら)のように消えてなくなり
残ったのは横顔
あなたの白い横顔
青い空 はたちよしこ
電車の中 前の席には
髪を後ろに束ねた女子高校生が
参考書を読んでいた
定規で答えを隠しては確認している
膝には 紺色のカバン
下を向いた顔に 髪が触れている
ずっと 以前だった
わたしは
じぶんの 生きている意味の答えが
わからないまま 苦しかった
そんなある日
車窓から 吸い込まれそうな青い空をみた
ただ 美しいと思った
そのとき
強く 生きていきたいと思った
いま 電車は
ゆっくり カーブしていく
車窓が 吸い込まれそうな青い空を流していく
そのとき
窓からの まぶしいひかりに
高校生の横顔が輝き
顔をあげた
小さな時間 はたちよしこ
おかあさんと
小学六年生くらいの男の子が
それぞれの自転車に乗っている
二人は 前になったり
後ろになったり
笑顔が浮かんでいる
家に帰ると
きっと おたがいに忙しいのだろう
けれど いまは
ゆっくりと自転車に・・・
なにを 話しているのだろう
いつもなら言わないことも
話しているのだろうか
二人の 小さな時間が
ゆっくりと
自転車に乗っている
エルゴレア
アルジェリア・サハラのオアシスにて 下前幸一
エルゴレア
焼けた砂
行き場のない
白昼の
堆積する
日の履歴
風化した遺跡に
言葉は届けない
割れた土
燃える道路と
荒地
砂漠の墓地
沈黙
投げかける言葉も
会話もなく
ただ踏む
ズックの音
フランスパンのサンドを頬張り
コカを飲みながら
揺れる自らの影に
なすこともなく
行き着けない
理解をもてあそぶこともなく
ただ運んでいく
一歩一歩の
無意味の
意味の
根源
オアシスは遠く
営みからも
遠く
*
影ひとつない
荒れた大地に
焼けた大気がショートする
見渡す限り
誰もいない
ただ
焼けた土と
砂と岩
遠くにマッチ箱のような建物と
やぐらのようなものが見えた
荒れた皮膚のような大地が
静かに燃えていた
幾度も僕は振りかえり
僕自身との距離を計っていた
エルゴレア
言葉以前のものに
僕は晒され
僕は
僕のなにかを
乾かしたいと思った
夏の日の午後 左子真由美
Qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse?
いったいお前はどうしてしまったのか
おまえの青春を*
朗読の声が
しずかな教室にながれて
ことばが黒板に書きとめられてゆくと
過ぎ去った時間のなかに
忘れていた場面が
ふとよみがえる
(朗読がヴェルレーヌの詩だからなのだわ)
おまえの青春に
何が見えるか
たくさんの悔恨
果たせなかった夢
落日に
長い影を曳いて
通り過ぎていったものたち
(夏の日の午後にはたまに永遠が見えるんですって)
そんな日には
垂直に時が降りてくるから
不意をつかれたように思い出す
たいせつな最後の一行
あの日
見失ったことばを
そして
熱く寂しい時間の森のなかを
もう一度彷徨いはじめる
*Verlaine『Sagesse(叡知)』より
神々が生きてある場所 葉陶紅子
薄衣の襞は 女神の豊満な
裸身を揺らす 匂やか色の
射抜かれて盲いた目には あざやかに
裸身は匂う 不滅(とわ)のいのちの
女神らが歩みし後の 残り香を
たよりにめぐる 空の境界
美しき入り江に 青き影落とし
分け入る波の 恍惚を思(も)う
傷口にあてがう 薬草のごとき
聖域は在る 現実(うつつ)に双(なら)び
日常と重なる 間(あい)の境界に
永遠は彳(た)つ 馨しく笑み
永遠はなが身のうちで 目ざめ彳ち
匂える肌を 地上にはこぶ
裸線に棲む鳥 葉陶紅子
裸線に棲む 鳥ら惰眠をむさぼりて
星の雫の 虹色を聴く
南風は 裸線の文字を攪乱し
洋墨(インク)の青に 鳥は目覚むる
遺伝子に折り畳まれた 鳥たちは
ひと声鳴いて 空に舞い上ぐ
鳥たちが描く裸線は 宇宙(コスモス)の闇
虹色に 裂き染め明かす
聖猥は鑠(と)かしてひとつ 昼空に
遊べや鳥ら 鳴き交わしつつ
射殺され 鳥は裸線の巣に帰り
廻廊を抜け 宇宙を産む
生者/死者つなげる裸線 鳥たちは
枝先に止まり 風に揺れいる
鳥 升田尚世
あなたよ
次は
鳥に生まれてほしい
ぼくは小さな虫になる
空に向け
すっと一本
青く弧が伸びる
太陽を背に
塗ったみたいな影を作って
気づけないスピードで
あなたは
ぼくを食べるのだ
その腹は熱いから
きっとすぐに溶けるだろう
それとも
時間をかけて
ぼくでなくなっていくのか
少しばかりのドロドロに
地に落ちる
陽に乾く
風に吹かれる
雨に混じってしみ込んで
ささやかな養分になる
草の葉が青く育ち
また弧を描いて
露を浮かべる
そこに小さく空が映り
鳥は気づかず
過(よぎ)るだろう
散歩道 加納由将
この先に何があるんだろう
早く見てみたい
霞のドレス着て
駆け出しいていく
かすかにそう「潮」の香り
もう待ちきれなくて
気づかずに駆け出していた
体は透けて二重に見えるけど
かまわないんだ
早く見たいから
一直線に足が勝手に早くなる
そこに何かがある気がして
早く見てみたい
ただそれだけ
業平忌 加藤廣行
ありやなしやととへば
あらはれたる
したたりのやうな
花のひとひら
ならばここが
おもひをやすめる
うたまくら くさまくら
ゆるしたまへ
ひなのまどろみ
こひごころほとびはてて
たびのしとねかとただすものあり
いづかたへと
しらすじゃない 白井ひかる
ジッとこちらを
見つめている奴がいる
――俺はしらすじゃない
しらすの三杯酢を作ろうと思い
冷蔵庫からパックを手に取ると
訴えかけるような鋭い視線に気がついた
四角い発泡スチロールのトレーのど真ん中
日の丸弁当のように
白いしらすに囲まれて
異物のような形の小さい赤い物体が
ポツンとひとつ
顔を近づけてよく見ると
タコだ
一センチにも満たない体に
胴や尖った口や吸盤の付いた足がちゃんとある
水ぬるむ春の海
いっせいに出漁するしらす漁の船団
大海原に次々に投げ入れられた船曳網を
真っ青な海に漂う純白の天女の衣だと
タコは見間違えたのだろうか
早く逃げよと叫ぶ兄弟姉妹の声も
彼の耳には入らなかったに違いない
自らしらすの大群に迷い込み
彼の命運は決した
あなたがしらすでないことは
わかっているよ
タコさん
少年の夏 斗沢テルオ
夏休みの自由研究の定番 昆虫標本
この時期になると雑貨店の店頭に
標本セットが並ぶ
コルク栓の小さな小瓶に
得体の知れない液体 そして玩具の注射器
朝早くから裏山に入る
トンボにセミ カブト虫に蝶
捕獲しては小さな紙箱に入れ虫ピンで
(そうかあれは虫ピンと呼ばれていたんだ)
踠(もが)く昆虫を真上からひと刺し
さらに注射器で謎の液体を注入
ミイラ化させる薬だ なんて
悪ガキたち皆 信じ込んでいた
今思うにあれはただの水だった きっと
水でも空気であっても踠き続けた昆虫は
やがて箱の中で絶命する
ずらり標本として並んだ昆虫の個体
じっと真上から見つめ
成果にニッと口角上げ蓋をする
休み明けの教室はミイラ化の比べっこだ
731部隊のことを知ってから
あの昆虫たちが
記憶の底から時々這い出てくる
あかいふく 吉田定一
あかいふく 脱ぎ捨てて
太陽が めをとじる
西空にたらたらと あかいふく
いつの日か 見たっけな
おっかさんの 背の上で
燃えていた ぼくの街
姉六歳(むっつ) ぼく四歳(よっつ)
ひぐらしが鳴いていた
綺麗に片付けられた轢死体の その線路脇に佇む 母と袈裟を纏った僧侶。そ
の側を 列車は傲慢にも 悲しみをふっ飛ばして通り過ぎる。「運転手の嘘っ
ぱち。耳の聞こえないものが 自殺などするものですか。」喉を詰まらせるよ
うな 母の嗚咽の声…。
「あなた 覚えている? 空襲警報が日夜鳴り渡ってね。その度に恐々(こわごわ) 浜寺
公園の南端にあった農業博物館へ逃げ延びるのが精いっぱいだったのよ。重い
中耳炎を煩わっていた智子を 耳鼻科へ連れて行くことさえ出来なかったの。」
線路にこびりついた肉片を菜箸で拾いながら「ご免よ ご免なさいね。」と合
掌して母は悔む。「あの時 戦争さえなかったら 起こらなかったら…。」母
の呟く哀しみが いまも天の高みにつり下がっている。
美しく発狂して 清らかな廿千(はたち)のいのちを散らした姉さんよ。夏が巡り来るた
び 遠い記憶の岸辺を姉と彷徨(さまよ)いながら 今も 終わることのない戦争が…
亡き母と幼い姉を連れて 八月の夕暮れる哀しみの向こうからやってくる。
あかいふく 脱ぎ捨てて
太陽が めをとじる
西空にたらたらと あかいふく
いつの日か 見たっけな
おっかさんの 背の上で
燃えていた ぼくの街
姉六歳 ぼく四歳
ひぐらしが鳴いていた
註 筆者が四歳の頃、空襲で夜、母親の背におんぶされて近く
の浜寺公園(堺市・高石市)にあった農業博物館に逃げた
とき、大阪湾北東の海岸沿いの海と空か燃えるように赤々
と染めていた、その記憶が今も消えないで脳裏にある。空
襲で堺の街がすっかり消失した時である。その日が、昭和
二十年七月九日のことであることが、枡谷優氏の著書、記
録『大阪戦争』の一文で初めて知ることができた。
洗濯物を干す 関 中子
草臥れた
たいしたことはしないのに
椅子に座って静かにしていただけなのに
三月に五月だなと感じて なんだか草臥れた
どうしようもないので 草の実になる
飛び出したい気になって 実を確かめる
用意はまだです 花を咲かせていないので
断られて 見ればつぼみも充分でない
どうしようもできずおとなしく草臥れた
夜になって眠った
砂漠で眠る女の夢を歩いた
途方もなく眠りつづけたようで
眠り草臥れたっていうのに 雑木の上で眠る
予定がしっかり浮かんで
終バスへ走りこんで
買い損ねた洗剤を買い
目覚めて風が少ないのが幸いする
昨日に継いで今年二度目の三月の五月 洗濯物を干す
よく乾いた
たいしたことは起こらないが 充実した
黄金色の時、黄金色の日 佐倉圭史
正午の中心街で、
私はもう以前の様に勢い良く歩けなかった
しかし、
私は閉じていた心を開いてみた
「心のみ」を、開いてみた
すると、
そこに入り込んで来たのは
周囲の人々の流れる心だった
他者を想う心、愛する心
(それらが私に向けられたものでなかろうと)
開かれた心に入り込んで来た
そして、
私は勇ましく歩いた―黄昏の中心街を―
黄金の夕陽というものが
丁度人々の愛に美しい色を着ける頃を
知らない自分を 西田 純
自分の知らない自分を
ぼくは 見てみたい
自分には 自分が見えないから
鏡にうつすように 詩に書いても
平面にしかうつらないのは いやだ
見たところだけ ではなくて
見えないところまで 見たいのに
オーケストラのなかで 弾いてみる
前から 後ろから
右も 左も いろんなパートと
からみ合わさって
自分も あらゆる楽器とかかわりあって
ぼくの音も いっしょになって
とけ合って
今まで気づかなかった音色も出て
自分自身を
空から 聴いてみよう
ザルツブルグの鐘の音 水崎野里子
ザルツブルグでは
たくさんの鐘が鳴った
石畳の小道を歩くと
教会の前を通ると
お城を見上げていると
洒落た小さな店を覗いていると
突然
カンカンと軽い音で
鐘が鳴った
鐘楼を見上げる 鐘の音が空から降る
時刻を知らせてくれているのだろう
朝? お昼? 夕暮れ?
人々は悠然と舗道のテーブルで
食事をしている 仲間とおしゃべり
コーヒーやワインを飲んでいる
私と夫はぶらぶら歩き
河を渡ると旧市街
大聖堂の前に
大きな広場がある
モーツアルトの銅像を見上げると
ここでも 鐘の音が鳴り渡る
お城と教会が多い街
教会はどれも古い面影で
ステンドグラスと
マリア像や聖者の像 天井画のダイナミック
アレクサンダー大王の英雄譚
古さと時代がそのまま居残る
ザルツブルグ大聖堂は大きな宝物殿だ
司教のレジデンス 教会 修道院まで
偉人の肖像画 風景画
マリア像 キリスト像 黄金の聖拝
大司教のミサ飾り 宝石が散り嵌められている
眼を見張る見事さ だが これは他所でも見た
モーツアルトが生まれ
育った家 父レオパルドの名がある
ザルツブルグで バイオリンの名手だった
アマデウスは何人かの兄弟姉妹の一人
観光客で一杯だ 小さなピアノ
クラヴィエが片隅に置かれていた
あら 昔父が買ってくれた 小さな
練習用のピアノみたいね
大聖堂前の広場は 広大だ 俗と聖とがごったがえす
モーツアルト広場に モーツアルトの彫像が立つ
土産物屋やレストランに人々が群れる
折からザルツブルグは音楽祭の最中
モーツアルトの像の下に置かれたピアノで
次々と若者はピアノを引き継ぐ
城(シュロス)と教会(キルヘ)がしばしば同じ
そう気づいたのは 去る少し前
そこでモーツアルトは生まれた
ザルツブルグは塩の街 エーデルワイスの歌の街
ケバブというエスニックのランチ
大通りの脇のテーブルで夫と気軽なランチ
気軽なおじさん 小さな食堂 ケバブは美味い
オーストリアは移民が歩く すこやかに歩く
コーラはどこにでもある
雑多な思い出の中で 今 ひたすら鐘が鳴る
鐘よ鳴れ 降れ 雨のように
喜びの 涙のように 光のように
路上の乞食の女の上に 去り行く旅人の上に
ミラベル城の庭園の 色とりどりの花々の上に
赤い薔薇の庭園の上に
涸れて落ちる 花びらのように
私たちの詩の上に
モーツアルトはオペラが巧い
シェイクスピアの軽い喜劇の味を出します
(二〇一九年八月十八日~二十三日)
<PHOTO POEM>
ステージ 中島(あたるしま)省吾
嫌い、とは贅沢
好き、とは贅沢
野良猫ちゃん夏アッツイから水道管の鉄の上で寝てた
野良猫ちゃんでも援助の飼い猫か、野良猫かも選べない
私は夜、水道管の鉄の上で寝てる野良猫ちゃんにちくわやる
幸せそうに、好きそうにすりすり、むしゃむしゃ
人間は、嫌い、と選べる
嫌いな人間なら警察に突き出して、彼らを崩壊させることもできる
人間は、好き、と選べる
贅沢な境涯だ
仏教によれば
行いによって
次のステージがあるという
畜生界とか言ってられない
最上の菩薩界や
人間として王さまの子供の生まれなどの天上界行きは
宝積の今現在の生活だ
<PHOTO POEM>
交わらない糸 長谷部圭子
わたしの心の糸
あなたの心の糸
絡まないように
もつれないように
切れないように
複雑に変化しないように
まだ 交わらない糸でいたい
指 平野鈴子
めぐりくる季節
もう芽を持ちあげてきたかとまちわびる
蕗の薹
天ぷらにしようか 蕗の薹味噌にしようか心が躍る
熱湯にくぐらせた蕗の薹にふれると 黒茶色のアクで指が染まる
ほろ苦い春の使者に 喜びにひたる
木ノ芽や花山椒
実山椒が出廻り 大量の軸を取る作業で指先はアクで黒ずみ爪先まで痛む
次の日も指先の色がとれない
とっておきの珍重される花山椒は どの場面で使おうかと心が弾む
細く刻んだ紫キャベツが 青紫色に指を染める
甘酢に漬ければ 輝くような若い娘のようだ
そして美しい紅色となり 食卓を飾る
秋になれば 落果した臭気と戦いながらの銀杏の処理
果肉を取れば白い銀杏が 秋の味覚の一役を担う
明日の美味しいのため 包丁研ぎで夜ごとまた指が汚れる
清潔に切った爪を保ち ネイルサロンには縁がないわたし
皺・シミ・切り傷・火傷もした この指
しかし 永い風霜を共に経たこの指がいとおしい
日本の四季を楽しみ ささやかな食を楽しめるのはこの指があればこそ
抱きしめて 平野鈴子
「あなたの目 悲しい目をしているね」と女性画家から心ならずも聞いた言葉
私は動揺した
絵を描く彼女の洞察力に感服してしまった
「どきり」とした言葉に胸が詰まる思いがした
そして分かってくれる人がいたことが安堵の気持ちにつながった
*
三歳になっても乳離れできなかった妹
母の乳房に「へのへのもへじ」や辛子
泣いて騒いで断乳した
長い間母を独占し続けていた
「姉ちゃんだから」のいつもの言葉が独り歩きし抱きしめられた記憶がなかった
娘には背中でおんぶをし腰を痛めるほど長い年月であった日々が蘇る
しかし娘を抱きしめたことが思いだせない
突っぱねて抱きしめなかったのではなかったかと不安がよぎる
娘に聞く勇気もないこの息苦しさ
*
知人の若いママから長男誕生の便りが届いた
お姉ちゃんをしっかり抱きしめてあげてねの言葉と共にお祝いを送った
私の言葉が不用意でお気に障ったのか
全く返信もなく年賀状さえなくなり四年が経過
消しゴム判子の出羽三山
ゴルフ道具を載せた車と共にアデューなのか
世代間のギャップは埋められなかったようだ
*
いつも優しい理解者であるご婦人が見守ってくれている
屋外で急に私を抱きしめた
余りにも唐突で狼狽したが心が安らかになり
体中に温かいものがめぐり涙をこらえるのが大変だった
ただわけもなく嬉しかった
沈黙 川本多紀夫
銀色に輝く飛行船が
何かの徴のように
音もなく中空に現れて
何かの恐ろしいことが
起こる前のように
あたりいちめんに静寂がひろがる
かつて 鉤十字マークをつけた
大きな飛行船が現れたことがあった
それは幻のように見えた
それから ほどもなく
不吉な予兆は 現実のものへ
地獄絵図の様相を呈して現れた
……
終末の主の日が来るまえに
預言者によって
メシアが遣わされると伝えられながら
そのことは起こらなかった
いや メシアは一度
遣わされたのだが
十字架にかけられて
葬られたという
それ以来 幾ばくもの世紀が経ち
アウシュビッツ から
トレブリンカ から
ブーヘンヴァルト から
『あなたは 何時来られるのですか』
何度も訴える声が
あったのに
何時までもつづく静寂
神の沈黙
無常観 中島(あたるしま)省吾
夜、八時ごろ
暗くなった四階の階段で座り
近くの神社の祭りの提灯を観ている
対立宗教、日々題目の兄ちゃん
隣の家の娘さんには嫌われている
娘さんが出てきて
兄ちゃんと無視
缶コーヒー買ってきてあげようと
想っても誤解されたら
嫌だから
無視で素通り
寂しいお母さん死んだ
独り暮らしの兄ちゃん
娘さん、彼氏らと改造車で夜遊びに行く
人生の旅 中島(あたるしま)省吾
近所のアラフォーの生活保護者男性が
できちゃった婚、福祉世帯として
生活保護産まれた時から両親が受けていると
近所の弁当屋さんで自慢していた家庭の女性に結婚させられた
もう、軽々しく話しかけられない
男のみと子ども食堂こんちくしょうと話が合っていたのに
バレンタイン奥さんに護られて
バレンタイン奥さんに罵声で殺されそうになった
上下観ろと
旦那に(王子さまに)偉そうに言ったから
偉そうに言ったらあかんで、と
五百円で示談や
と、賠償と奥さん
すいませんでした。と私
私は天涯孤独の独りもん、下っ端だ
野良猫ちゃんが一生懸命
ゴミ箱あさってたので
ちくわやった
菜の花 弘津 亨
あなたの恐怖は わたしの恐怖であるか
あなたの絶望は わたしの絶望であるか
悲しみも また――
地震や戦争そして事故の悲惨な映像を
見せられ見せつけられ わたしは憂鬱になり
たまには涙ぐんだりもするが それは
わたしが安全であることの証である
あなたの家族の死はわたしの家族の死ではない から
あなたの
国 あなたの故郷 あなたの子ども あなたの
友人 あなたのたくさんの――
どこまでいっても わたしのではなくてあなたの
くじのようなものだ
癌を患った知人のことばを
散歩の途上 ふと 想い出す
くじとはずいぶん軽いな と思ったが
なにも言えなかった
そのときの 戸惑い
を 反芻しながら
行きつけの公園まで歩く と
いま 春である
花壇では 菜の花が満開で
その花の黄色いボリュームが
あなたの恐怖と絶望と悲しみに
正確に釣り合っていて わたしを
驚愕させる