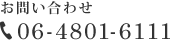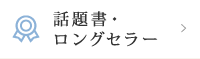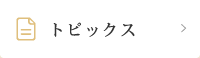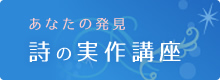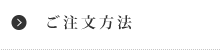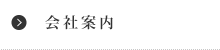![]()
154号 恋
154号 恋
- 屋根の毬 佐々木洋一
- 母さん 帰ってきてくれないか 司 茜
- 歳のせいで 清水恵子
- 愛を待つ 岡崎 葉
- 窓 本多清子
- 金星 本多清子
- 情熱 水田 雪
- アミーゴ シルブプレ みちる
- 木霊 登り山泰至
- 夕暮れ 登り山泰至
- 日輪幻想 瑞木よう
- 寺なるもの ハラキン
- 時間なるもの ハラキン
- 爪 吉田定一
- 野生の自分 加納由将
- 少年よ木に登れ 斗沢テルオ
- 挨拶 日野友子
- 小詩篇「花屑」その6 梶谷忠大
- 虹に乗る 蔭山辰子
- 死者と春 藤谷恵一郎
- 尺取虫 藤谷恵一郎
- 月夜 弘津 亨
- 全能 神田好能
- うつら うつら 神田好能
- 幼馴染 藤原節子
- センサー 藤原節子
- 久しぶり 星ノ深千夜
- 信太あたりで日が暮れて 河井 洋
- 不安の壺 木村孝夫
- 花屋 佐古祐二
- 肖像VIII-XIV 葉陶紅子
- 鳥人 葉陶紅子
- 雪女郎 牛島富美二
- 傷 晴 静
- 男が女を守る ~男は殺されに行くこともある~ 中島(あたるしま)省吾
- 噂の二人 原 和子
- 半殺し 原 和子
- 子どもの日が過ぎて 斉藤明典
- 桐の木 根本昌幸
- 待つ―コガネグモ 山本なおこ
屋根の毬 佐々木洋一
ふと見上げると屋根に何かのっている
毬だろうか
毬だ
鋭角に照らす陽ざしや風雨の力感に押されながら
耐えることではなく朽ちること ひたすら在ることで
毬がまりであったのはいつ何時であったか
屋根の内で転げ はずみ 引っ掛かり
置き去りにされ 忘れ去られ
毬はまりをすて
はずむことも転がることもなく
まりと言われることもなく
あれはどの子の活力から放たれたまりであったか
ふと見上げた屋根に顔をのぞかせている
毬だ
てんてん てんまりの 手がそれ
それから忘れ去られ
それからふくよかさを失い
屋根の一隅に引っ掛かったまま
だれからも忘れ去られようとして
忘れ去られまいとして
在ることが そぞろに朽ちてゆく
母さん 帰ってきてくれないか 司 茜
蝉が鳴いている
一週間を生き切った蝉なのだろうか
生まれたての蝉なのだろうか
か細く鳴いている
真夜中の風呂あがりに
爪を切っている
「夜 爪を切ったらあかん
あれほど言うたのに」
あの世から
せわしなく団扇で顔をあおぎながら
血相変えて帰ってきてくれないか
母さん
新聞紙 ひろげて
手と足の爪 二十本
バシバシ切る
「癌は移らんそうやから
ここにおいてな」
母さんは言った
どう答えたのか
思い出そうとすると 泣けてくる
いまなら
やさしく抱き寄せ
ヨシヨシできるものを
蝉は
落ちたか
飛んでいったか
誰かが
口笛を吹いて通っていく
歳のせいで 清水恵子
萎(しお)れて縮んでいく音に巻き取られるために早くと
かたちに合わせて重なったことも
縮めば縮むほどきつくからまって
枯れたことも枯れてもまだ抱き合っていたことも
各々方はご存じあるまい
抱かれている もしくは抱いている
どこから見ても一枚の
二人はいつだって葉にもなれた
蕊と葉脈のせめぎ合いが一番楽しかった
どんぐりころころを追っかけて
どぜうと遊んだこともあったっけ
生まれて初めて肺門まで濡らして
深いほど好き濃いほど好き溺れるのが好きと
息の限り歌ったけれど
二人とも立派な音痴だったねえ
醒めた背にまぶす粉が足りない
空気をふくめふくめふくらめ
(並んでばかりいても花は忙しい)
(咲いたまま別れても花は騒々しい)
梢のpiriodo
も
藻のutopia
も
汗のSeptember
も
幸いにして忘れた
御無沙汰いたしておりますが、
眠たい眠たい日々であります。
おかげさまで。 かしこ。
追伸
明日 毛根のDNAを鑑定します。
愛を待つ 岡崎 葉
君は愛の志願者だと
青春期にある人から言われた
振り返って そんなにも愛がほしいかと
さりげなく思い 不安になり
ほんとうは愛がほしいのではなく
愛が足りないのだと気づくまで
途方もない時間が流れた
こころの空洞に吹きつける風なら
どんな受け止め方でもできる
けれど愛の足りない者は愛を知っても
愛を持続させることができない
そうやって一生を寂しく送るのなら
美しいことばに逃げ込んで
軽くなろうと
やがてその行為は紙片となり
幾度も地上を巡っては
いつしかあの日のように
声をかけてくれる幻影を待つようになった
ただ一つの愛も たくさんの愛も
この世界にはあふれ過ぎ
あふれる泡で人々は窒息するだろう
ほんとうは誰ひとり
愛に満ちた者のいない世界で
窓 本多清子
病室の窓は
大きな キャンバス
パレットの絵具
赤は
患者の血液
青
先生方の手術着
白
カテーテル 手術機具
大きな モニターテレビ
灰色
患者の涙
キャンバスに画(えが)かれたのは
だれかの
自画像
六、七日たった頃
どなたかが
キャンバスの絵を
消してくださった
もう一度新しいパレット
エメラルド
キャンバスいっぱいの空
銀色
ゆっくり流れる雲
うすべにいろ
キャンバスいっぱいに
そよ風のうたう声が
たゆとう
金星 本多清子
初冬の くれがた
淡いみずあさぎの
西南の空に
星 ひとつ
〝宵の明星 かおだした―〟
幼い頃の かすかな唄声
屋根と木の
わずかな すき間を
オペラグラスで のぞく
雪の結晶か
黄連の花のようなものが
くる くる 円舞しながら
きらめいて
時どき 暗雲にとざされる
わたしの心
遠い宙の
西の夕星(ゆう づつ)
あまつみか星が
見守っていてくれるよう な
もうじき、つぼみが弾ける
名前も知らない小さなつぼみ
こんなところに
とろとろ燃える情熱の火を
かくし持っていたなんて
アミーゴって
ぼくは いった
いみは わからないけど
ごろにゃーごって
コジイが いった
ぼくには
いみは わからないけど
シルブプレって
ぼくは わらいながら いった
ぴちょぴちょぴーって
ピーコがいつものように いった
ごはんできたわよって
ママがきて いった
ぼくは
いただきますって
スプーンをもって いった
テレビが
うたをうたってた
おちゃわんが
かちかちって いった
神社の境内にある大木に
背をあずけて瞑目していると
木霊が寄ってくる
木霊は私の周囲を跳ね回り
初夏の陽光に女性めいた笑い声を溶けこませながら
そうして私に笑いかけるのであった
私は意地悪く半目を開けてその姿を探すが
杳としてその姿は知れない
揺曳する半斜視の視線は精霊の不在を知って
哀しげにまた閉じられた
けれどただ声がまだ森閑とした中に漂っていた
心が聞いているのか
私は今度は注意深く耳を澄ませた
揺動を続ける謳うような笑い声を探るうち
背中の大木の根元に行きついた
太根に耳を押し当ててみると
そこに聞いたのは流動する静脈の音
大容量のあつい熱の流れが内側を貫流しているのであった
それは春風に騒ぐ名も知らぬ虫や花の静かな音と
交響を織りなし
小宇宙のオーケストラの奏者の一員と成った
大自然へのチケットを持たない私は
もぐりの聴衆というバツの悪さも
人という異邦の種族に我が身の所属することも忘れて
眠りの行きつく席に背をあずけ
大地の叫びと木霊が歌うのを聴いていた
交響がクライマックスにさしかかった時
微かに薄く視線を開けた先では
青白き焔が少女の形容をとってステップを踏んでいた
それは魅力的な躍動を誇る焔の舞踏であった
白地に烈しく刻まれた憂鬱の模様
赤々と燃え上がる白百合の筒袖に
一叢の雲鶴が表れだし
彩なる竜巻の息となって大地の影を濁す
彼方への抛物の線の距離はいよいよ長く
はらはらと泣き腫らした眼を充血させ
煙の匂いを都会のはらわたは
吸い取っていった
憤りをさみしく広野に走らせ
ほろほろと明日にしおれる
そのほとばしる葛藤の渦を
麻のように千々に細裂いていく
しわしわのキャメルの底に書かれた
ひとり夕暮れ
金環蝕の日の輪にめらめら立ちあがる 火の触手巻いて プロミネンスが踊る あたりは一瞬で 暗く肌寒く 隠れた太陽の形 三日月の形そのままに 葉の上で 風にたくさんの三日月形の影が踊る 草の葉に光が踊り 蜂の羽音がかしましい 耳元で 蜂の羽音は遠く近く 鳴り踊る 草原は白いクローバーの花が覆い 蜜集めに忙しかった蜂たちは一斉に花から離れ せわしなく 飛びまわる 驚愕の金環の日 生き物が動きまわる うろたえる 闇が深まり 気温が下がる 不安が心を覆う 光が 熱が失われていく 皮膚 風が冷たくなる 数分間 日常が陰る 一瞬で呼び起こされる不安 ある日突然降りかかった厄災の日 黒い海が乗り上げ壊し 押し流した 驚愕の驚天動地の日 炎が走り 舐めていた冬の日が 今にでも起こりそうな 体の震え プロミネンス踊る 寒くなった世界はまた 光を取り戻し 暖かくなる 世界はまた輝き 太陽に額を向けたくなる
基壇づくりを皮切りに
礎石を据えて
数十本の柱を
あらよっ といっせいに立てた
「風蝕による破損はなはだしく
高欄がいまにも落ちる状況」
マスをのせ上にハリをのせた
ケタを架けわたした
「肘木の組手個所に破損
そして隙間がひろがっている」
ケタに垂木を架けるなどして
全面に板をはり破風をとりつけ
おびただしい瓦を
せいのっ といっせいに葺いた
「心柱全体にひび割れ部拡大
補強済み」
仏像群を安置した
読経をはじめた
「天井板および支輪板の
彩色文様の剥落いちじるしい」
以来一千年を経て
金堂に鎮まる
見返り如来に
なにごとかを祈り続ける夫人がいた
境内の一角に
樹脂単管バリケード カラーコーン
鋼管群 AKフェンス A型バリケードトラ板付
さらにブルーシート
などの縄張り
江戸時代後期の
居酒屋で飲んでいた四人は
不意に思考してしまった
江戸時代後期の夜の屋内がこんなに暗いとは!
メール!
クルマ!
江戸時代後期の町人の冗談は古臭い!
だからといって時代劇ではない
江戸時代後期の居酒屋で
まさしく飲んでいた
思考してしまった途端
まわりの町人たちが
別次元のようになり
酒をたのんでも通じなくなった
四人の来世が
不意に脳内を
占拠したのだと説かれた
四人は時間なるものから処罰され
中有となった
古代を舞台にした
映画のロケでは
大勢の古代人役にまじって
三人の古代人がいた
立てた爪を胸におさめて
爪を切る
切った爪は
生の川原に零れ落ち
ひとはこうしていつも
優しく別離(わかれ)を告げている
闇夜に緑の星を忍ばせて
爪を研ぐ猫
おまえも哀しいかな
無防備ではいられないのだね
爪よ、今日は背中のかゆさに
よく手がとどく…
哀しいおもいの淵を
宥(なだ)めいたわるようにして
ひとときの優しさをなぞっていく
爪(おまえ)よ
かけていく太陽
動物は
殺気立ち
無益な
殺生を
くりかえし
人間は
恐怖心すら
忘れて
観察し
歓声を
上げる
野生の心は
死んだのか
いや
ここにいる
不随意運動
くりかえし
呼吸困難にすらなって
苦しんでいる
金環日食の朝
地球が誕生したとき
大地から先ず双葉が飛び出した
やがて根を張り幹伸ばし枝拡げ
地球を支えて―四十六億年
木は黙って立ち続けてきた
少年よ
今一度木の前に立つのだ
物言わぬ木から学ぶのだ
拡げた枝の分
根が張ることの意味を
蟻が這い鳥が巣作る木肌の温もりを
物心ついたとき
君の前に木はあった
本能に突き動かされ登ったあの日
大きな枝に腰掛けた達成感
木は葉先震わせ祝福した筈だ
人は大人になると
木に登ったことなど忘れてしまう
だから今一度
木に登っておくのだ
そこからは
東に人間の来し方
西に人間の行く末が見えるだろう
天突く幹は君の進む道を指している
木は黙っていても
いつだって君のそばにいるのだ
末っ子が就職して
家を離れた今春
私は なんだか落ちつかなかった
何かが うずうずして
ぷちぷちと皮膚を突き破って
出てきたがっている 気がして
ああ
なんて むかないことをしていたんだろう
親 なんて
私が
出てきたがっていたのは その言葉と翼であった
飛べる
根拠のない確信が私を励ますのである
舞台を終えた俳優のように
私は晴れやかだ
翼をぐぐぐっと広げ
天井を仰ぎ
脚を屈めて
礼ーっ
早苗田
1
水を張つた早苗田
その水平な水面に
ちひさなちひさな風波が
ななめにななめに流れてゆく
2
水中を田植機が
ゆつくりゆつくりと進む
後部の歯車が
ゆつくりゆつくりと廻る
クランク運動をする爪が
ちひさなちひさな早苗をつまむ
早苗は水中に立つ
風にそよぐ早苗よ
3
あはれ風にそよぐなゆ苗よ
今し方植えられたなよ苗よ
ほそいほそい米草よ
あはれ風にそよぐ
やよあやふげな風情の
なよ苗よ
4
風にゆらゆるままに
早苗の細根は
水中の粘土にすがり立つ
その隙をぬうやうに
さまざまな微小の蟲どもも
うごきまはることであらう
山里
この山里の五月の薄暑の
のどけさのなかを
鳥であらうか
蛙であらうか
その啼き音がひびきわたる
ああおまえはもつと何か
とてもたいせつなことを
夏のかすみのなかに
さがしてゐるのか
光景
白詰め草の白い花もずいぶん汚れてきた
柘榴の花が咲きはじめた
朱いろのちひさな喇叭のやうな花が
茅花流し
一束の白髪のやうな草の穂が
いつせいにいつせいに
風に靡いてゐる
どこかとほくへと吹いてゆく風情に
この東風は
茅花(つ ばな)ながしとも
あゆの風とも
あいの風とも
がらす戸に
枝葉の影がゆれる昼下がり
微睡(まど ろみ)を叩くのは
かすかな風の騒(ざわ)めき
お願い お願い
霞の床を揺らさないで
光の衣をまとう
妖精の手招きに
誘われるまま
舞い上がる
そこは いつしか
七色の橋の上
眼下に九寨溝の流れ
鯉の鱗の数ほど
日の光の輝き
振り向けば
深緑の水を湛えた
白根山の火口湖
水辺から水池に架かるという
虹の橋
地球に点在する淵沼から湖沼へ
七色の桟橋は
国境を越えて果てしなく
彼の地へと繋がる
ふと
衿もとの冷気
すでに西の空は
淡い紅に
がらすに映る枝葉に
小鳥の影が加わる
一刻の午睡
邯鄲 黄粱も欺くとも
こよない 白昼夢に
ささやかな 祈りを託し
死者の胸に
小鳥が
一粒の種子を落とす
春
芽吹き
子馬の誕生のように
花を咲かせる
生命の宙の
ひとつの確かなものとして
死者は
ようやく大地に帰る
細枝に
のんびり 時間を食べて
尺取虫
何を測っているのか
恩寵のかたちに 丸く
宇宙を抱いて
宇宙に抱かれて
十一月の夜
天文学と無限について書かれた本を読む
石で造られた高い塔に登った男が
暗夜の空を見上げ
夜ごとに 星々の運行を追う
限りがない夜空のひろがり
を 男が無限と名づけたとき
男は なにを知りえたのか
星々の数を数え終えようとして数えきれず
夜空の果てを見極めようとして
眼差しはついに届かないままに
無限などというものは
考えるべきでない と
書かれた数式のうえに とまどいの表情を遺して
中世の学者は立ち去っていったが
この時刻
有限であるわたしが
無限について考える という逆理を
十一月の夜を昇ってくる月が
蒼く照らしている
どんなに頭の良い人でも
全能ってことはないよ ね
どんなに信じる人のことも
百%信じることは無理
お医者様でも
大好きな恋人でも
時々はうたがったり
やいてみたりする方が
人間らしいよ って ふふふ
言ってみるのも良いかもね
ベッドの上で うつら うつら
平和 幸せ
やさしい介護の人の笑顔
もったいない時間が過ぎてゆく
もっと苦労をするはずだったのに
これで いいのか
しなければならないことは
あるはずなのに
ベッドの上で 頭の中だけが
働くようだ
不幸ではないというのに 何を求める
うつら うつら と
「わたし見送りには
行けない涙が出そうだから」
たったそれだけの文だった
都会の大学に進学するために
故郷を離れるわたしを
駅に見送りに来た数人の
近所のおばさんのひとりに
あなたは
この手紙を ことづけた
物心ついた頃から
毎日一緒に遊んでいた
一つ年上のあなた
あぜ道でつくしを摘んで
煮て食べたり
畑で採れたてのじゃがいもを
摩り下ろして
でんぷんを作って
おやつにした
あなたが学校で
習った歌を口ずさむのを
わたしは耳で覚えて
一緒に歌った
山に押しつぶされそうな
狭い谷間の村を
逃げ出したくて
広い世界で羽ばたこうとしていた
十八歳のわたしは
遠い未来ばかり見つめて
地元に残った
あなたの寂しさも気づかず
返事も書かなかった
齢傾き
はるか西の故郷を振り返ると
残照の中に浮かび出るのは
幼馴染のあなたが
わたしにくれた
旅立ちの日の
あの短い手紙
長患いに
塞ぎこんでいたら
いつの間にか
水仙が咲いた
オレンジ色の口を開いて
自分の歌を歌っている
いつ誰が植えたのかも
忘れられていたのに
土の中で
季節を察知する
センサーが
球根に合図するのだろう
今があなたの出番だよ
咲きなさいと
わたしの体の
センサーはもう壊れたのか
早く合図を送ってほしい
地下で休眠しているわたしを
いつ起こしてくれるのだろう
久しぶり
元気?
って声をかけたくて
長いこと会えなかったみたいに
ちょっと感極まるみたいな
久しぶり
元気?
太陽に空に
雲に
また 会えた喜びに
変わって
あなたにも
急に会いたくなる
男にハンドルを任せると
女は決まって眠ってしまうのでした
男はほどなく
前方からの危険を回避する他の全ての意識を
追憶の中に置いてしまって
春なのか秋なのか、冬なのか夏なのか
道は狭いのにまっすぐにのびていて
御祭礼の提灯が
どこまでもどこまでも続いていて
後部座席には、ちっちゃかったころの吾子が二人
兎の抱き人形の耳の片側ずつを
獲物を分け合うように咥えて眠っていて
切なさが極みに達し、とめどなく涙がながれ―
提灯のかげに隠れていた紅灯が闇に鈍く滲みだすと
それが覚醒の合図なのか
男のおもいは、唐突に打ち切られる
「この道あまりにも長すぎるね」
女は薄目を開けてスマホのナビなど覗いて
「アンタ、また曲がるべき角を見落としましたね」 と
女は残されている自分の存在理由の全てを
男の育ての妻(母)と規定して
自分が眠ってしまうと(男は)きっと道を間違えるから
今度は眠るまいとして
堅いオカキなどポリポリするのですが
やはり、胸に白い尾のようなものを抱えて
また、正体なく、眠ってしまう のでした
人は誰でも 不安の壺を持っている
蓋のある壺なのだが
大きさは それぞれだ
蓋の開け閉めを頻繁にしている人
蓋が錆付いたまま放置している人
ときどき 思い出したように蓋を開ける人
蓋を開けたまま閉め忘れている人
蓋を閉め忘れた人の壺は
一番大きくて重い
今まで 一度も開けたことがない人も
この頃は 頻繁に
壺の蓋を開けるという
開けると
生気をなくしたような顔色になるから
まわりから診察を勧められる
人への伝染はないのだが
心気するものに
思わず開けてしまう人もいるらしい
原発事故から三年が過ぎ
補償の線引きがやっと終わったものの
古里は何も変わらない
心療内科は
予約制なのだが
このような新患が増えているという
壺を持ったまま
診察室で
じっと名前を呼ばれるのを待っている
名前を呼ばれると
ドクターは壺の大きさをまず確かめる
蓋閉めを忘れる人には
壺の中まで
丁寧に診察する必要があるのだ
ときどき ドクターも
顔色を悪くしたりしているから心配だ
同じような訴えばかりだから
その気持ちが伝染したのだろうか
壺の大きさはまちまちだから
症状を聴きながら
壺の中を覗いたりもする
壺の中には
たくさんの不安が入っているから
治療する症状の
しぼり込みには時間がかかる
だから 診察室の中は
ゆっくりと時間が流れていく
壺の中では
不安の数が増えたり減ったりしているが
カルテに書き込む
症状の一つ一つに未練はない
人は誰でも 不安の壺を持っているが
壺を見せ合ったり
壺の大きさを競ってはならないのだ
屈託の夜の歩みに
街の一角が明るんでいる
花屋には
とりどりの花がにぎやかだ
若い娘たちが
おしゃべりしているようで
精気あふれる様は
僕にはまぶし過ぎる
店先の明かりに
悩ましい心ごころをうち捨て
花々の美しい精に
見入って後
街角を曲がると
通りはさらに暗いものの
かなしみの中にも
何故かほの明るい心を運んでいる
ラファエルロ 花弁を口にふくみつつ
神の国描く 瓜実顔に
数式で語るメルヒェン トランプの
逆さにむすぶ キャロルとアリス
多足類エロスうごめく 斜かいの
額の皮下が 棲みかのシーレ
鏡わり 砕いた顔のすきまから
こぼれる言葉 拾うがデュカス
道化面はずし見すえる 尖り顔
モンテヴェルディ どちらも同じ
瞑想するバッハの楽譜に 惑星は
アリアを歌う 対位の軌道で
貝殻に宇宙(コス モス)をみる バシュラール
髭づらうらは 幼子の夢
晴れた日に撃たれしものは 鳥になる
地図に画けない 都会の森で
鳥顔になり 空高くつき入れば
地上に満てる 異国の言葉
雲の上(へ)の 惑星(ほ し)のふちより放射さる
光の粒よ 砕けし顔に
いつまでも 夢見る直ぐなものたちは
動かずにいる 樹や石のごと
揚力は 鳥の囀りまねぶ喉頭(の ど)
虹の飛沫(しぶき)を くぐりて滑る
見ればいる そらせばいないそれだけで
無辺の空に 国はあらわる
広げやる 双翼の辺(へ)のわずかだけ
心かろめば なが領土なり
雪道を歩いていると
朗らかな足音と鼻唄が
わたしの後ろに湧いてくる
振り返って見るけれど姿が見えない
わたしは何度も雪道を曲がりながら
恋人の家へ向かっているのだ
空には七星がくっきりと冴え
道々の木々には木魂がささやく
わたしの脚は
悪路にはまることもなく
寒風は心地よく頬を撫でて去る
わたしの耳には
どこまでもスキップとハミングがついてくる
ふと立ち止まって
恋人の窓の明かりを確かめる
スキップとハミングも立ち止まる
振り返って見ても誰もいない
ああ、これが噂の雪女郎
ふっと気づいたけれど
初めて出合ったこの夜更け
鼻唄交じりの雪女郎だなんて
わたしはひどく雪女郎を気に入ったのだ
ヘッドホン到着
ヘッドバンドは本革製
イヤーカップは本革張
オシャレ感覚につい惹かれ
無理して落札四十数年前の年代物
愉しみ奏で続けてくれていた
ヘッドホン
感謝の気持ちをつい忘れ
手放し今は手元になし
はやる心で好みの一曲
・・・信じられない
・・・信じられない
瑞々しい音色が・・・
枯葉の旋律さらさら拡がる
イヤーカップに数か所
あて傷押し傷
四十数年奏で続けてきた証の
あて傷押し傷
愛おしくさえ想える
手放すことはもうない
愛機になった
セントリアから羽田に着いた
僕はあの人に言った
「にゃんとかしてやりゃあ」
『いったいどうすりゃっての』
「大丈夫。君が悲しいんなりゃあ僕も犠牲になりゃーから。なんとかしてや
りゃあ。たとえば君を苦しめるもの僕の持っているマシンガンでたたき殺
すから。男が女を守るとは命をかけること。たとえば警察に殺されても君
の安心を見たいから」
『バカじゃない』
「死にたいくらい悲しいわ。
きみのためにけいさつにころされてもきみのいたみからあんしんをまもる
じぶんでありたい」
僕は恋色の犬 どうしようもない薔薇の君
香りがある
ものすごく優しくてしなやかに心細い心を笑顔で包んでくれるあの純な香り
人間誰しも悲しみを笑顔に変えてくれた人に愛を感じるのは当たり前
まだ君の素肌に密着していたいスケベな僕
僕は愛を知った
柔らかくて
優しくて
心地良くて
紛れも無い冬に咲く向日葵のようだった
愛の空はピンク色の脳に染まるけど
心はスカイブルー
何とかする
僕は男だった
夏空の下 君を馬鹿にしている飛行機のジェット音
「大丈夫。君が悲しいんなりゃあ僕も犠牲になりゃーから。なんとかしてや
りゃあ。たとえば君を苦しめるもの僕の持っているマシンガンでたたき殺
すから。男が女を守るとは命をかけること。たとえば警察に殺されても君
の安心を見たいから」
『バカじゃない』
「死にたいくらい悲しいわ。
きみのためにけいさつにころされてもきみのいたみからあんしんをまもる
じぶんでありたい」
君の愛は僕を愛してくれる
愛の体が殺されるのを黙っていられない
忘れられる筈がない
君が困った時には
僕が泣くようじゃなく僕が殺されに行くこともある
「なんとかしてやりゃあ」
『バカだわ・・・』
「にゃんとかしてやりゃあ」
『いったいどうすりゃっての』
「大丈夫。君が悲しいんなりゃあ僕も犠牲になりゃーから。なんとかしてや
りゃあ。たとえば君を苦しめるもの僕の持っているマシンガンでたたき殺
すから。男が女を守るとは命をかけること。たとえば警察に殺されても君
の安心を見たいから」
『バカじゃない』
「死にたいくらい悲しいわ。
きみのためにけいさつにころされてもきみのいたみからあんしんをまもる
じぶんでありたい」
僕は恋色の犬 どうしようもない薔薇の君
噂の二人が 隣にいる
大きな屋敷の 家つきばあさんと
最近すべりこんできた 元校長先生の
ツルのようなじいさん
カラスが 早速
屋根の上から からかう
カア、カア、カア、イイナー、アッホー
朝食の キウイを取っていたじいさんは
すっかりカラスの気分になって 答える
カア、カア、カア、イイヤロー、アッホー
―あら、あんがいと
おもろいおじいさんやないの
とたんに 私は見直す
だが まさか塀のこっち側から
カア、カア、カア、ウラヤマシイナー、アッホー
と 声を揃えるわけにはいかない
縁側から
太ったばあさんが 身をのり出して
花やいだ声で
あら、センセ、いつまでもそんなとこで
なにしてはりますのん
じいさん やおら目をむいて
アホ、わしゃここで
ずっとキウイちぎっとるだけや
―あら、センセ 居候のくせして
あんがい いばってはるんやね
カア、カア、カア、イイキニナルナ、アッホー
海を 死ぬまで見続けていたいひとと
海を
死ぬまで 見ることのできなくなったひとに
情ようしゃなく
珍島(チン ド)の海は 満ちてくる
なんの屈託もなく
呑みこんでいく
油の浮いた 水のなかで
ひとは
愛する者たちと共に
溺れ
あがき
足をつかみ
抱きよせ
この世での
いのちの尽きるまで
くり返し くり返されるこの残酷
何百人 殺したのか
何千人 半殺しにしたのか
連休に来た子どもや孫が帰り
静かになって 聞くカセットテープ
好きな歌をダビングしたものだ
「ゆりかごのうたをカナリヤが~」
夜中に目を覚まして泣く子を抱き
低く歌った なにか涙が出てくる
「いつのことだか思い出してごらん」
三月 幼稚園のお別れ会
懸命に歌う姿に 止まらなかった涙
子どもの姿が今の孫の姿に重なる
この子たちにどんな未来が残せるのだろう
二年前 投票権を持った大人たちは
しあわせな(・ ・ ・ ・ ・)ファウスト博士になって
メフィストーフェレスに魂を売ってしまった
富める者がますます富む「旧」自由主義
戦争をする普通の国
多くの犠牲を生んで時計が止まる その前に!
ぼくらは一本の苗木を貰った。
それは桐の木だった。
それを手に持ち
ぼくらは学校を後にした。
さようなら
またいつの日にか
ここで会いましょうと 言って。
もう遠い遠い日のことだ。
それは昨日のことのように
思い出される。
桐の木はすくすくと伸び
すぐに大きな木となり葉を付けた。
桐の木は伐られて
売られていったが
その根元からまた芽を出した。
そういうことが何度か続いたが
もうそれもなくなってしまった。
僕は今も思う
あのすくすくとまっすぐに伸びた
桐の木のことを。
あれはぼくらがおとなになっていくことだった。
ぼくの心の中には
いつも いつまでも
一本の桐の木がすっくと伸びている。
降り続いた雨が止み
青白い月が昇った
コガネグモは ツゲの枝先に忙(せわ)しなげに網をかけるや
真ん中にぶらさがる
待つ
待つだけでよいのだ
ギンヤンマが
キラリと羽をひけらかして消えようと
ギー チョンと
草むらでキリギリスが鳴こうと
待つ
待つだけでよいのだ
だが ひょっとして モズのはやにえ
ヤモリの胃袋におさまらないものでもない
コガネグモは チョッ と舌打ちし
かくれおびに爪をかけなおす
すっかり青白んでしまった網
うねうねと通り過ぎていく時間を
ちろちろ舐めながら
コガネグモは 空中ブランコをつづける