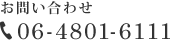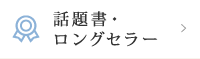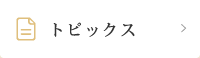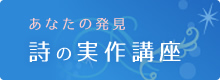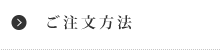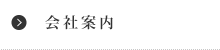![]()
159号 像・イメージ
159号 像・イメージ
- 夢を買います 本多清子
- いのちの代償 大倉 元
- ホテルで 神田さよ
- ときめき 大瀧 満
- 死亡欄 大瀧 満
- 石ころ 吉田定一
- 黒衣となって 青山 麗
- 青磁 原 和子
- 鶏頭 山本なおこ
- 雪の森 瑞木よう
- 市長が代わる 丸山 榮
- 思いが心に泊まるとき 下前幸一
- 北辰の冬花火 斗沢テルオ
- カラス 根本昌幸
- COOL STRUTTIN' 葉陶紅子
- 果羅黒 葉陶紅子
- 夏 中西 衛
- 投壜通信 藤谷恵一郎
- 一朶の火 藤谷恵一郎
- シボレート 藤谷恵一郎
- カウンターで 加納由将
- 影踏み 木村孝夫
- 冬の風 晴 静
- ゲバラ大好き 蔭山辰子
- 思想 ハラキン
- 十字路 ハラキン
- 政治家に ハラキン
- 触れる 清沢桂太郎
- 僕の唇を奪った養護施設のkiss 中島省吾
- 空蝉 牛島富美二
- 掌を見るとき 牛島富美二
- 詩がぶつかって 関 中子
- 窓 水崎野里子
- 処暑 日野友子
- 白蝶草 佐古祐二
- 残してみたい言葉 神田好能
夢を買います 本多清子
胃と腸が 時どき 叛乱をおこします
心臓が 山奥の火の見櫓のように
力なく たえず半鐘をならします
流れの悪い溝は 痰がつまって
四六時中ぞろぞろ出て来ます
象の足のようにはれあがって歩くのがつらいです
こんなになっても 生きていかねばなりませんから
夢を買っては いけませんか
夢をみては いけませんか
夢を食べては いけませんか
夢に口づけしようとしている
少女になっては いけませんか
いのちの代償 大倉 元
戦後七十年
忠義兄が骨となり故郷祖谷へ戻って七十一年
戦争はむごい 三百万人余の命を奪った
兄もその中の一人
病院とは名ばかりの施設で病魔と戦い
戦場へ出られないすまなさ もどかしさ
戦友たちのいたわりの言葉 冷たい目
堅いベッドで思うように動かせない体
いつも思い出すのは故郷祖谷の山々
父や母 弟や妹
産まれてまもない十人目の僕のこと
いつか日本へ 祖谷へ戻れると
がんばっていたと
僕は思う
死の伝達人が
白い布で包んだ箱を持って
急な坂道を上がって来た
昭和十九年八月十五日
忠義兄はビルマで死んだ 二十六歳
母やんは箱を抱きしめ泣いた
泣き声は祖谷の山々にこだました
忠義兄を知らない僕の涙も止まらない
カナカナ蝉が泣きじゃくっていた
箱を振るとカラカラと小さな音がした
兄のお骨が入っていると信じ裏山へ埋めた
母やんは忠義よ 忠義よといいながら
いつまでも土を盛っていた
祖谷の人々は麦や芋を主食に生きてきた
僕の家は父やんが病弱だったので
それよりひどかった
母やんは一言も言わなかったが
僕にはわかっていた
忠義兄が学校に行かせてくれたことを
いのちの代償
「遺族年金」
ホテルで 神田さよ
真夜中
壁を越えて
連続音
床を踏んでいるみたいだ
不愉快な不明
壁に穴
みつからない
暗い部屋
穴があくほど見つめる
音はますます早くなる
ラジオの音量を大きくして隣りにも聞こえるようにした
床音は鳴りやまずさらに速度を増し行進しているようだ
繰り返す幾何学模様
闇のなかの抽象のヴォイス
朝食に行こうと廊下に出る
もう隣りのドアーは開いて
だれもいない部屋に
古びた軍靴
こびりついた黒い泥
あの日は雨だったのか
ゲートルが床にだらんと落ちている
鼓膜が震える
快晴の日の
警告
ときめき 大瀧 満
いくつになっても
ときめいていたい
としをかさねればこそ
ときめきがほしい
やさしく
やわらかく
いちごいちえの
ときめきをしてみたい
あやまちは
あやまちとして
ほろにがくのみほし
いまのいまをときめいていたい
ああ いくつになっても
ときめきがほしい
じーんとしびれるような
いのちのかなしみのような……
死亡欄 大瀧 満
新聞をひろげると
死亡欄が気にかかり
若くして亡くなられた人は
私より何歳下であったか
運よく長生きした人は
私より何歳上であったか
と ぼんやり
かぞえてしまうこともあるが
古来より
いのちは天からの贈りもの
とは言うものの
あと グラスに五分の一ほどの
いのちが残っているとしたら
さて、どのように飲みほすべきか
とかなんとか
酒場の片隅で小理屈をならべ
昨夜も晩くまでグラスを玩んだのだ
もうそろそろ
死亡欄に近づいているのも知らないで
石ころ 吉田定一
地上にあっては
少しも冴えない顔をしているのに
水の手に 取り戻されると
その瞬間 石ころは
水底で 夜が明けたように輝きだす
頑固な顔は こども顔のように揺れ
身のまわりに 小さい虹をつくって
あどけない孤独なうつろいを漂わしている
億光年の暮らしの中で
失ったものが いま静かに蘇るのか
想い起すように 溢れるように
火の山から吹き出た 太古のどよめきを震わして
ああ、激しい渓流の波立つ流れの中にあっても
苛酷な衝突と闘争を繰り返してきたおまえだ
風雨にも打たれて 角も取れ
すっかりまるく 滑らかな表情になっている
深いふかい水底で 頑なに閉ざした沈黙を
意思を 柔らかく解きほぐすがいい
そして魚のように泳ぐがいい
もう奪われ 失うものはなにもない
石ころよ
黒衣となって 青山 麗
あの日あのとき
女が少しでも伝えていれば
閉ざされた男の心は動き
同じ道を歩いていただろう
あの日あのとき
京都の街中にある小さな神社の境内
黄色い銀杏の葉がハラハラと散っていた
男と女は何となくその凋落を見つめていた
今思えば 二度とない巡り会いだったのに
あの日あのとき
未来を知らない二人の間には
ただ風が吹いているばかりだった
愚かな悔恨とはこのことをいうのだろう
しかし あの日あのとき
誰かが黒衣となって女に寄り添い
そっと耳打ちしていたなら きっと
黒衣は今宵の女自身 あの瞬間に戻りたい
可笑しいほどほんの僅かな違いだったのに
ときは流れ 女は白い道を独り歩み続ける
青磁 原 和子
窯の業火をくぐり抜けてきたなんて
信じられない
陶工のむくつけき手で
逆さまにされ
撫でたり
さすられたりしただなんて
思いたくない
季節の届かない ロビーの一隅から
せわしない心を抱いた
足早のわたしを
遠い 遥かな 清らかな声で
あなたが呼びとめたとき
そう、あなたは
海の向うの 仙境の
幾重にも山深い 神秘の湖の底から
たったいま 引き上げられたまんまの
そのまんまの
色と かたちをしていたんだもの
鶏頭(けいとう) 山本なおこ
いつもの帰りの道で ああ誰かに見つめられて
いる そんな気配がして はっと振り返ると
鶏頭の花だった いままで目に止めたこともな
い 立派な鶏頭の花が赤々と燃えるように咲い
ていた
鶏頭は にわとりのかしらと書くように 鶏冠(とさか)
が 一茎にひとつどころか 四個も五個も付け
ていて まるで四、五匹の鶏がひとつの茎の上
で 鶏冠を寄り添いながら 天に向かって鳴き
叫んでいるようである
さながら火が燃えるようないきおいで 花を咲
かせ 鳴きながら いまをいまの自分を燃え尽
くさんばかりである ああ 台風が来るという
今日のこのときになって 凛とわたしを振り返
らせて目にする鶏頭の花 不思議な一期一会の
ひとときである
翌朝 台風一過 空はなめらかな青ですべすべ
していた 両手を挙げて背伸びしたくなる朝で
ある 鶏頭のことが気になり 行ってみると
思ったとおり毅然と空を見あげていた わたし
も一緒に空を見あげて思った このひとときに
栞(しおり)をはさんで いつでも振り返られる日にした
いと…
雪の森 瑞木よう
雪降る 森
針葉樹から 積もった雪の束が
時折固まりになって 降り落ちてくる
風に吹き流されて 雪が走る
私はそれをガラス越しに見ていた
暖かい部屋には炎が燃え
ガラスは透き通り 外の景色はよく見えた
何を待って この部屋にいるのだろう
ある日 天啓のように降り下りてくるものか
あるいは なにもない 空か
ほてった てのひらを ガラス窓に押し付けると
雪が消えていく
雪の奥には針葉樹林
そのむこうは白く掻き消えて
風の音がいつもやまない
市長が代わる 丸山 榮
昨年 市長が代わった
どうも前の市長の後を そのまま引き継ぐのが いやであるらしい
今まで使っていたエコ車が 黒塗り大型車に代わり 机や椅子も代えてしまった
上野千鶴子さんの講演が決まっていたのに それもキャンセルしてしまい 全国的
にバッシングをうけ 再び お願いしたそうだ
市庁舎が移転したので その跡地に 木造の図書館と市民の憩いの場を 設計し
基礎工事も始まっていたのに それも取りやめてしまった
今は 更地となって 駐車場になっている
こどもの夢も 市民の夢も 羽がはえて飛んでいってしまった
一番頭にきたのが 万葉の森の 破壊だ
万葉集の歌に詠まれている 木や花や草を 根こそぎ 切り捨ててしまったのだ
何年も 何年も 年月を重ね育て上げてきた 癒しの森であったのに
ああ なんという もったいない ことを
残っている 公園の木々は 赤松や桜の大木をのぞくと ササやアジサイばかり
味気ない 趣もない 普通の森に 生まれ代わってしまった
大人に成りきっていない 首長や議員が 日本中に はびこりだした
なんとも 嘆かわしく こわい時代であることよ
思いが心に泊まるとき 下前幸一
思いが心に泊まるとき
影の訪れはほの青く
べきことを畳んで行きましょう
日の暮れは遠い
始まりはもっと遠い
糸口は風に揺れている
いまも隔たりは深く
消えたなにかには届かない
誘いの場所は
砂の音韻にさらわれて
そして私ひとりが
冷たい広場であるように
ささやかな毎日が
足元の滅びに立ちつくす
痛ましい喪失と
道連れに安堵を知りなさい
忘れたことを顧みて
色彩のない季節の
滲む記憶に
投げた約束を見失い
待ちぼうけふと
思いが心に泊まるとき
熱のない切実な空っぽであるように
そして私ひとりが
冷たい広場であるように
名前のない無数の佇み
リズミカルなリフレイン
軽快な楽隊の
傷ついて倒れたコール
錯綜する沈黙のガラクタ
そして私ひとりが
冷たい広場であるように
言葉は何も語らない
踏みしだく足音と
私は風景に拘束されている
今足元に夏の日差しが張り付いて
それはなにかを隠しています
石橋のベンチでひたと
思いが心に泊まるとき
私ひとりが冷たい広場であるように
北辰の冬花火 斗沢テルオ
凛とした北天の星野に
花火はよく映える
凍てつく夜天光に一瞬の煌めき
僕たちは何を願うだろう
夏の風物詩を
冬にもってきた奴は
きっと何かを祈ったはずだ
高く高く
一番高いところで弾ける火の玉
ひとつ弾けてあの人を想い
ふたつ弾けて家族を想い
星辰に弾ける大輪に
自らの来し方行く末を想い
人生も花火のように
一番高いところで
弾けて終えるなら
どんなにステキか
見上げる冬花火の向こうから
四百光年の北辰の光
僕らの立ち位置を見つめている
*十和田湖では毎年冬「十和田湖冬物語」と銘打って
巨大な花火を打ちあげ、湖面の冬を彩る。
カラス 根本昌幸
カラスのやろうめが
アホーと鳴いて行きやがる。
アホーのおれに向かって。
カラスのやつめ
山にかわいい七つの子がいるって
ほんとうか。
おまえたちは町へ出てきては
悪いことばかりをして
帰って行く。
もっとも人間も悪いのだけれど。
山に餌がなくなって
町へと出てくるのだから。
それにしても最近
カラスの数が
めっきりへってきた。
放射能には敏感だとは
聞いてはいたが。
やっぱりほんとうなのか。
ウソではなかったのか。
カラスには臭いがわかるのか。
おれにはさっぱり臭いはしない。
悪知恵のあるカラスだ。
そのぐらいのことは
すぐにわかるのだろう。
仕方がないな
アホーといわれても。
アホーと鳴くから
アホーと返事をしてやった。
COOL STRUTTIN' 葉陶紅子
Slenderな 脚線が紡ぐstepは
気位高き 多弁な視線
小賢しき目と口を撥ね 脚線の
勁いbeatが 開け放つ視座
脚線のtightなrhythm 鋭角に
青い破片(かけら)へ 都会をし切る
破片(かけら)へと砕く 都会の隙間より
覗き見るもの 匂い立つもの
幾つもの破片(かけら)嵌めこみ 新しき
都会の顔を 描く脚線
街角の先の 真青の領域に
脚線は跳ぶ 翼を着けて
脚線は虹を弾きて 昼空の
彼方に続く 憧憬(しょうけい)となる
果羅黒 葉陶紅子
果羅黒の盲いた夜に ひとり坐し
無一物たれ 客人(まれびと)として
わがなかで獣と暴れ ながかたち
毀損せしめよ 粒子と消えよ
屍骸(しかばね)は胸に抱きて 宇宙(コスモス)の
無限に交ぜん 裸線と消して
一千の果羅黒の夜を のみほして
胎児となって わが子と生(あ)れよ
わが乳房吸わんとすなら ひとたびは
死して生まれよ わが子と生(あ)れよ
なが粒子わが汁にとけ 宇宙(コスモス)の
始源(はじめ)をたどり かたちとならん
両の手で2つに裂きし 断端の
目に沁む新た 明日は生きなん
夏 中西 衛
風が裏木戸の扉を叩くと
さっと扉がひらく
母屋の誰もいない部屋に
上がり込んで
さっと抜けていく
ひとりごと
涼しいね
畠仕事の手伝いの合間
あい変わらず遊び呆けている
工事現場のトロッコを動かし
歓声をあげる
じゃれあって
もつれ土手を転げ落ちる
電信柱に耳をくっつけ
電流が流れているのを確認する
みんな息してるんだな
太陽が笑っている
街からバスが着く
厚化粧の
風変わりなおばさんが降りてくると
みんな珍しそうに取り囲む
おばさんは迷惑そうな顔をする
八月のある晩七時ごろ
向かいの高い山の空が真っ赤に染まった
焼夷弾落下の爆発音が聞こえる
隣家の和子ちゃんと見とれ
悲壮な気持ちになったのを覚えている
あれから
玉ねぎの皮が一枚一枚むけるように
少年から少しずつ脱皮していったような
気がする
投壜通信 藤谷恵一郎
一編の詩に千の魂が寄り添っている
一枚の絵に千の魂が寄り添っている
泥になり水になり
あるいは今でも漂っているかもしれない手紙
絶望に狂う大海を
一匹の蝶のように
百の詩が波間に消えても
一編の詩が流れつく
千の絵が空に燃え上がっても
十枚の絵が燃えずに残る
家族に見せたかった絵
先生や友だちの前で読んでみたかった詩
心を支え癒してくれた絵や詩 その時間
絶望の空の下で
絶望の大海に託したもの
未来の岸辺に届いた
詩や絵は
波間に沈んでしまった
みんなのもの
一編の詩に千の魂が寄り添っている
一枚の絵に千の魂が寄り添っている
――『テレジン収容所の 小さな画家たち詩人たち』
(編著・野村路子 株式会社ルック)を繙いて
一朶の火 藤谷恵一郎
一朶の火よ
我に我を明かす火となれ
我に我を顕す火となれ
一朶の火よ
追いつめられて 幾重にも幾重にも
追いつめられて
一つの生命が命のオードを
レジスタンスのように
叫ぶ その炎となれ
歌う その調べとなれ
一朶の火よ
不遇と貧困に喘ぎ踠く
一つの生命が
力尽きるとき
優しき火となれ
標の火となれ
な消えそ
一朶の火よ
シボレート 藤谷恵一郎
日本の川と
日本の花と
日本の風と
日本の季節が
盗られていた
たちまち
シボレートとなる
日本の川と
日本の花と
日本の風と
日本の季節が
渡河不可能なものによって
*『シボレート―パウル・ツェランのために』
ジャック・デリダ(岩波書店)より
カウンターで 加納由将
静かな時間
液晶画面に
洋画がながれ
音声は消され
洋楽が
流れる
カウンターに
座ると
コースターが
出されて
氷の音
ジントニック
何も言わず
離れていく
人通りは
途絶えがちで
時折
車が通る
音もなく出される
一口飲んで
目を閉じる
頭が空っぽに
なって
疲れはスツールから
地面に氷が解けるように
浸み込んでいく
大きく息を吐く
時間は止まっていく
ゆっくり
影踏み 木村孝夫
影踏みをしている
逃げる影法師を先回りして
キャーと言っては
また逃げる
でも この遊びは
すぐに飽きてしまうんだよ
僕が僕の影法師を踏んでみても
面白くはないからね
昔はたくさんの影法師がいて
競い合いながら
踏みあったんだよね
それが本当の影踏み遊びだと
思っていたんだ
たった一人では
すぐに飽きてしまうので
今は 木陰に立ち止まって
飽きた時間を
ぼんやりとやり過ごしたりしているんだ
放射能を心配して
友達とその家族は遠くに逃げ
みんな それぞれの影法師を持っていったので
僕は一人ぼっちだから
残ったのは僕と僕の家族だけだから
狭いなと思った空き地が
こんなに広くなってしまったよ
一人で影法師を追いかけながら
汗いっぱい流しても
周り切れない広さができてしまった
この広さは全部僕のものなんだけど
キャーと
ときどき演技者になって
声を出してみるのだが
一人は一人なんだよね
もう影踏みの緊張感などはないんだ
緊張感まで
逃げてしまったのだから
戻ってきてほしいのだが
もう影法師も成長しているだろうからな
影踏みできる
背丈を越えているかも知れないな
もう一度昔に戻って
たくさんの友達と影踏みをしてみたいな
キャーと言っては
また逃げる
そこに友達が
影法師を追いかけてくる
そんな影踏みを
冬の風 晴 静
散りそびれ
枯葉一葉
さびしげに
冬に似合わぬ
風
やさしげに
さよなら小枝
枯葉一葉
ふわぁ ひらり
土におかえり
ゆっくり
おやすみ
想いを念じ
風
ふきゆきて
ゲバラ大好き 蔭山辰子
一九六一年から半世紀以上 目と鼻の先の隣国 アメリカとキュー
バが漸く手を結んだ オバマとラウル・カストロ両者の会談は何と
五十三年振り この国交回復で人々は平和を取り戻せるのだ
私がチェ・ゲバラを好きになったのもずい分以前 亡くなった夫の影
響もあるが 映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」を見てから増々
惹かれていった
医学生のゲバラが友人と おんぼろバイクで野宿したりしながら 南
米大陸を走り回った青春物語 そこで目にした虐げられた先住民族の
人々や 生活苦に耐える人々の姿に出合い 病院に留まり手伝いなが
ら人類愛に目覚めていく 貧しくとも医療や教育が受けられる平和な
社会を実現したいと 心に感じていく
メキシコで フィデル・カストロとの運命の出逢い 平等主義に同意
し 命をかけた三十九年の短い生涯のチェ・ゲバラだが 世界中の平
和を希む人々に 生き方の指導者としての尊敬は大きなもので言語に
つきない
日本の大阪の片隅で 八十才の老婆のファンの居ることを 伝えてあ
げて欲しい 人生斯くありたいものと感動を!
思想 ハラキン
雲がまとわりついてきて
数ミリ身じろぐだけで
汗ばんでくるなかを
俺は醸成していった
むっとする地表
苔とともにうごめく昆虫のように
苔のかたわらで
じっと微風に揺れる花のように
(人目につかない微弱な花)
いや苔のなかで
苔とともに
苔そのものとして
俺は醸成していった
石仏の足もとを蒸らし
はいのぼって
石仏の顔を覆い
ついに苔むして苔むして
思想を湿気で覆い
俺は熟成していった
いにしえ
海のむこうの
乾ききった思想を運ぶおりも
潮の湿気となって
思想を船内で醸し
俺は熟成していった
雨よ
叙情に流れる現象をやめて
湿気となれ
(もう恋を濡らすな)
蒸気よ
吹きつける客気を捨て
湿気となれ
雨の思想でなく
蒸気の思想でなく
まして
砂漠の思想でなく
火の思想でもなく
娑婆に隠れて風をいざなう
湿気の思想として
俺はさらに熟成せよ
十字路 ハラキン
巨大な十字路で
数十万の生きとし生けるものが
信号待ちをしていた
その舞台全体が
濃密なかげろうに覆われ揺れていた
数十万のおのれの実体は歪められ
「ここの赤信号は長いから
あらゆることが起こる」
老婆が
古代からのように
まんじゅうを食べていた
初老の男が
世界にわめいていた
赤ん坊は乳母車ごと
奪われようとしていた
古い軍人がしきりに敬礼し
戦争を続けた
妊婦が今まさに
妊婦を放棄した
「赤信号が実体だとすると
けっして青に変わらない」
背広姿の背中から
来世が出てきた
数えきれない細胞が
いっせいに癌化し
アジテーションをはじめた
巨大な十字路で
数十万の生きとし生けるものが
信号待ちをしていたが
誰かが右腕をふりおろすと
すべてがかき消えた
かげろうだけが揺れていた
「実体は無かったことに」
かげろうと契約した
政治家に ハラキン
強行採決は浅い呼吸でおこなわれた。「国民の安全を守るため」。政治家たちの怒号のなかで
政治家は満足感にひたっていた。世界は政治だけのようだった。細胞膜のとなりでは、うつ
ぶせになって林の下草に顔をつっこむと、ハンミョウとカマドウマとサムライアリがさかん
に活動していた。数億年の昆虫の世界が政治家に向かっていた。
またしても戦争の足音が聞こえる。「いや戦争をふせぐための法案である」と、政治家は一
族の遺伝子にみなぎって力説した。世界は戦争と平和だけのようだった。さらに覚醒すると、
水鳥が湖面に急降下し、小魚を食らった。戦争でもなく平和でもなく。野生の世界が政治家
に向かっていた。
戦争反対、戦争反対。大衆と名づけられた人々は、シュプレヒコールを叫び、反戦歌をうたっ
た。世界は反戦歌だけのようだった。デモ隊が渡った橋のたもとに、サックスをぶらさげた
男がいた。男の瞳にデモ隊は映らなかった。サックスはものすごい速さで咆哮をはじめた。
反戦の意味もない、恋愛の意味もない、音楽のかたまりが、デモ隊に向かい、政治家に向かっ
ていた。
平和への願いを描いた具象画の展覧会。政治家は招かれ、「平和はすばらしい」とスピーチ
した。世界は具象だけのようだった。せいのっ とどんでん返しすると、水平線や垂直線や
あらゆる図形やおびただしい色彩が、躍動していた。そして彼らは「平和」という名称以前
を瞑想した。抽象のこぼれんばかりの豊饒が政治家に向かっていた。
触れる 清沢桂太郎
今日 久しぶりに
隣で眠っている
妻の肌に触れた
妻の体は いつものように
柔らかく温かかった
しかし いつかは
冷たく固くなる時が来るのだと
思いながら 愛撫した
妻は
無言のまま目を閉じていた
僕の唇を奪った養護施設のkiss 中島(あたるしま)省吾
初めて僕の唇を奪った 心を許す古里でのkissの風景
人生の旅人たち 養護施設の中
同じご飯を食べてた仲間たちと交わした幼い人生の旅人とのkiss
忘れられなくて胸が張り裂けそうな人生の旅人とのkiss
まず最初のkiss
小学校四年生だった『はたボー』こと 畑村君(仮名)
『拝啓』脚が長くてかわいかった君
今 社会を生きている君へ
僕もあの時 中学一年生でした
施設のとき、みんなが遠足で外泊している日曜日
わがままだった 僕と君の二人 取り残されたね
日が暮れた 誰もいなくなった
養護施設の中 二人 自由時間の午後七時ころ
淋しかった想いをしていた二人だったから
君から「きすきすしよう」と書いたラブレターが僕の机の上にあった
甘い甘い少年愛の誘惑 くれたよね
甘い甘いチョコレートのよう
その夜 君と僕は何回も「きすきす」したね
本当に君の顔 かわいかったよ 少年愛の誘惑
『拝啓』今の君は小学四年生じゃなくて青年だよね
今 社会はあまりにも荒れています
『拝啓』あの時十歳だったかわいかった君へ
あの後 僕だけ施設の山田先生に怒られました
君と「きすきす」した僕と君ももう青年の大人
『拝啓』青年になった君の瞳は何を見てますか
今 社会は欲望だらけでたいへん荒れています
人間は汚いものだということをあちこちで見せつけています
僕の唇を奪ってkissした だから僕の唇と同じで踏ん張れよ
社会に負けないで頑張ろう
僕も頑張っているから君も頑張ろうよ
『拝啓』僕の愛を感じた幼かった君たちへ
『拝啓』問題だけど施設の中でkissした人がいっぱいいる
真由美ちゃん 知顕君 章久君 充教クン 妙ちゃん 沙織ちゃん
由香ちゃん 希美ちゃん 愛ちゃん 政一君 そして、実希たん
『拝啓』僕の唇を見た君たちへ
君たちの明日の風は君たちが創る
僕の唇を奪った だから頑張ろうよ
『拝啓』僕とkissした君たちへ
今 社会はひどく荒れて汚れています
さまざまな汚染は人間が創り出しています
欲望で人はあちこちで心の殺し合いをしています
頑張って 汚染された荒れた社会を生きようよ
今 君たちが独立して頑張って生きているということ
切望している 私も頑張っています
養護施設を出てからが君たちの本番だよ
明日は明日の風が吹く
空蝉 牛島富美二
一輪の蛍袋にしがみつく
空蝉を撫でていると
少しコトバがつながるようになった
あの日以来呑み込んだままのコトバが……
空蝉は誕生まで
地中生活二五五五日
世に出て七日
私はまだまだコトバを失っていてもいい
あの鳴声は
二五五五日を耐えた響き
溜まりに溜まった谺
限りある日々の歌声
空蝉となって
昼も夜もしがみついたままこれから
私にささやき
唄いつづける
掌を見るとき 牛島富美二
今日も
じっと掌を見る
あの日の掌と今日の掌と
同じではない
同じであるはずがない
拾ったもの捨てたもの
握ったもの触れたもの
みんな違っているから
それらに触れた掌はあの日から
同じであるはずがない
足だって眼だって耳だって
あなたのだって父のだって母のだって
あの日と今日は同じではない
一瞬一瞬違ってゆく
だから未曾有
吐く息も吸う息も未曾有
何もかも未曾有
だからだからだから
今このひととき一瞬を
命を懸けて掌を見る
詩がぶつかって 関 中子
長く
空に
とどまろう けれど重い
どうしようもできない
ぽつん ぽつん
堰は切り落とされ
泣く ごうごうと
ところ選ばず ごうごう
空にあい
なんとか
逃げのび
ぽつ ぽつ
詩が痛い
肋骨にひびいて骨折を複雑にする
窓 水崎野里子
目を閉じると
窓が見える
どこにもない
非在の窓
カーテンもない
ベランダもない
並ぶ花鉢もない
窓枠に飾る人形もない
でも確かに
私のこころを
閉じ込める
非在の窓
窓を開けようか?
青い風が
金色の蝶が
緑のふるさとが
飛び込むかもしれない
嵐の雲が
血に飢える獰猛な虫が
嫉妬の女神が
飛び込むかもしれない
窓を開けよう 今
そして入れよう
踊り狂う風を
絶望という名の希望を
希望という名の絶望を
生命という名の死を
死という名の生命を
目を閉じると
遠い窓
私の時間の中で
忘れられた窓
いつか見た窓
これから見る窓
非在の窓
実在の窓
窓を開けよう
そして閉じよう
入れた幽霊を
逃すな
処暑 日野友子
八月が行こうとしている
エノコログサも行こうとしている
ここではない どこかへ
茎を伸ばし
ころりとした穂を立て
季節を信じて 風を待っている
暑さは まだまだ厳しい
容赦なく照りつける陽に ひるむこともなく
アスファルトの隙間 隙間をついて
しなやかに広がる放射状の緑
エノコログサ
いつのまにか
どこからか来て
今 また どこかへ行く気だ
風をつかまえて
風をつかんで飛んで行こうとしている
―よい旅を エノコログサ
――ヨイ旅ヲ ヒト
挨拶を交わそう
一瞬だけ交差する生に
白蝶草(はくちょうそう) 佐古祐二
真夏の暑い日差しに晒されて立つ
白蝶草
長く柔らかな茎が
手を空に広げるように伸びて
尖端に
一つひとつ
小さな白い花をつけている
たっぷりと水を遣る
根が水を飲む
それは
見えない
だが確かに
茎は活き活きとし
たくさんの蝶が舞っているようだ
それは
見方を変えれば
茎が撓って
風さえ押し戻しているようでもある
自然体でありつつ
押し戻す力を秘めた
そのような個我で
私もありたい
注 白蝶草
ガウラ。別名、ハクチョウソウ、ヤマモモソウ。学名は
Gaura lindheimeri 。
白い花をつけるものと桃色の花をつけるものとがある。
夏の暑気にも芯の強さを持って長く花を咲かせる。花は
4枚の花弁と触覚のような蕊があり、ちょうど蝶の形に
似ている。
残してみたい言葉 神田好能
老いてはじめて言える
残してみたい言葉
それは むかしむかし
本の中で読んだ言葉
初めて知った
世界の人々の
淋しさ 悲しさ
老いて わかる
言葉のかずかず
それは衰えていく 今
聞きとれないけれど
聞きとれないのに 心に
言いたくても言えない言葉が
聞こえてくる
時にはあきらめの
時にはやさしい 声
時には聞かぬふりする
やさしい 思いやり
☆
老いたとて
愛の言葉は みなおなじ
老いたとて
世界の姿も みなおなじ
ちがうと思うのは
わたしだけが
まだ ゆきつかぬ
想いのなかにいるからだろうか
生きているうちは
さぐるもよしと
想いさだめて
行きつもどりつゆく日々よ