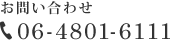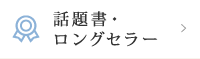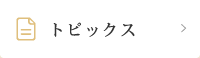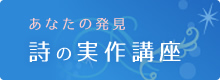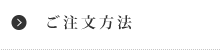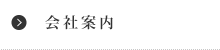![]()
157号 顔・フェイス
157号 顔・フェイス
- 背中合わせで寝ていると 下前幸一
- 農場跡 杉谷昭人
- どったらの木 原子 修
- 夏の森 林美佐子
- 傘のメモワール 水崎野里子
- 畳 山本なおこ
- 命の胎 藤谷恵一郎
- 樹と風とこども 原 和子
- 魔法 中島(あたるしま)省吾
- 空の箱 瑞木よう
- 浮かぶ 晴 静
- 世界 ハラキン
- 連鎖 ハラキン
- 生の否定 ハラキン
- キツネの嫁入り 藤原節子
- 父の言葉 根本昌幸
- ボンヤリ 加納由将
- 草青む 佐古祐二
- 古里 木村孝夫
- 天地と裸身 葉陶紅子
- ピグマリオン あるいは 導きの女(チチェローネ) 葉陶紅子
- 鷺 牛島富美二
- コップ 左子真由美
- うつり薫(か) 本多清子
- 窓ガラス 吉田定一
- 算数の勉強―『塵劫記』(吉田光由)に想を得て― 斉藤明典
- 関ヶ原の戦いまで 清沢桂太郎
- ホームに住んで 神田好能
- 天狗さんの顔 田村照視
- 戦友の死 田村照視
- ねこやなぎの花 蔭山辰子
- 食べる 弘津 亨
- 真っ青な空 関 中子
背中合わせで寝ていると 下前幸一
背中合わせで寝ていると
ぬくもりの波間から
音ない深夜のひと時に
ひとり箱舟が漂っていく
濃い紫の空っぽに
私の理由は溶けていく
遠い記憶の海原に
君と背中合わせで寝ていると
闇夜の耳鳴り
発芽する夢見は
島国の草葉の陰に
さみしい悔恨を抱えている
動けない場所
ざわめきの敵意
不確かな陸の静寂に
感触の確かさが消え入るときに
君と背中合わせで寝ていると
背中合わせのぬくもりと
侮蔑と、痛みと、悔しさと、
忘却と、自愛と、錯誤と、
不可能の社説が時のまにまに揺れている
赤丸の印の場所で
禁じられた原子野にたたずんで
腰折れた言葉を水面に葬り
顔色をうかがいながら
ゆらめきに
意を見失い
意に添わぬまま
私は懐かしいそこをはぐれていく
背中合わせに寝ていると
忍び足のスピードで
兆しが兆す
ほとぼりの冷たさを
オタマジャクシが泳いでいる
農場跡 杉谷昭人
畜魂祭の会場まえで蝦蟇口を拾った
この手で殺した牛たちを埋めた牧草地の跡だ
とび色の牛皮にはまだタンニンの手ざわり
口金には四月の風がうすく光っている
この古めかしい道具にはまだ新品の匂いが残っている
会場の入口には議員さんの姿がそろっている
どうやら統一地方選が近いせいだろう
そろっていると言ってもこの町では
町会議員の議席はたった八つだけなのだが
わたしたち牛を飼っていた仲間の姿はまだひとりも見えない
この町が口蹄疫に襲われたのは四年まえのことだった
三十万頭からの牛と豚がガスで殺処分されて
農場に掘った大きな穴につぎつぎ埋却されて
その上に菜種やコスモスの種子が撒かれた
〈畜魂碑〉と刻まれた一本の石碑が建った
生活のない土地が生まれて
記憶を作り出しようもない毎日がやってきて
わたしたちは慣れない仕事についた
道路工事 小荷物の配送 コンビニの店員
きょうはみんなが帰ってくるはずの日なのだ
畜魂祭のざわめきとともに拾った蝦蟇口を手にしたまま
わたしは いやわたしたちは何かをじっと待ちつづける
一年ぶりにあの髭面に会えるかもしれぬ
牛小屋の干し草の匂いが嗅げるかもしれぬ
足下の小石の蔭から一本の牧草が芽生えてくるかもしれぬ
どったらの木 原子 修
どったらの木に なって
生ぎるしか ね((ない))
ぐじゃもじゃの根っこ
地の大祖霊(おおじつちやん)の
臍穴(へそ あな)のまっくらくらに
どったら 生(は)やし
にょろくれる幹に
野垂れ死にの青い思想
さらさら 流してよぉ
枯れっ骨(ぽね)のまんまで生えだ枝っこに
虚無の葉っぱ
ぐじゃめかしてよぉ
咲きもしない 理想の花よ!
と
命懸(が)けで惚れた
馬鹿ったれの 吾(わ)
生(な)りもしない 此度(し ど)浄土の実(み)よ!
と
切なぐ焦(こが)れた
阿呆ったれの 吾
文明スイーツの毒蜜しゃぶる
都人(みやこ びと)よ さらば
地の大祖霊の臍穴に落っこった
吾 独り
どったらの木に なって
どろでろ地獄
負(おんぶ)っていぐしか ね((ない))
夏の森 林美佐子
少女たちの
駆けたあとに
あまい残り香が
ただよいます
蝉のなき声に
すいよせられて
少年たちは森の奥へ
消えていきます
老女のような
老木の私は
あなたと生殖できません
捕られていたのは
蝉ではなく
少年たちかもしれません
今夜
蝉は産卵管を
私につきさしにくるでしょう
あなたと新しい恋人は
土産物屋のような
避妊具屋に
手をつないで入るでしょう
少女たちの
残り香から
夏の初潮のにおいが
たちのぼるとき
老木のような
老女になった私は
少年たちを追って森の奥へ
消えるのでした
傘のメモワール 水崎野里子
あなたに会った時
私は雨の中だった
しとどの夜の雨
ちょいと差し掛けてくれた傘
二人で歩いた 交差点の信号まで
私はそそくさと横断歩道を渡り
振り返ってさよならと手を振った
こわかったの あなたの大きな黒い傘
ずぶぬれでふてくされていた私
あなた 教えてくれた
少女がひとり雨に濡れていてはいけない
ずぶぬれで歩いていてはいけない
今 私は帽子なしでは歩きません
でも歩きたい時があったのです
あなたはさっさと手を振る私に妙な顔つき
笑ったの? 怒ったの?
遠い 遠い 見知らぬ男
女に成りきれなかった少女には
大人の男の大きな傘が怖かった
大人になることは傘をさすこと?
羽を拡げたコウモリの相合い傘で歩けること?
川越街道 夜の雨
車は泣いて 深海魚
二匹の鮟鱇 泳ぎ別れる
畳 山本なおこ
畳に寝る
青い藺草(い ぐさ)の匂いがする
ひとつ
深呼吸
空のど真ん中に
いるような
海のど真ん中に
いるような
誰が来ようが
へっちゃらだ
何を言われようと
へっちゃらだ
来るなら来い
畳(ここ)へ来い
青い藺草の
故郷の匂いがする
命の胎 藤谷恵一郎
一人の少女の声が
世界に響いた
歴史に無垢な少女に
歴史の歪みを背負わせる運命に負けない意思が
百の銃口を恐れない勇気が
万の核兵器で護れないものが
億の金で生み出せないものが
多くの手に支えられて
死の嵐の中を
命の胎を明るませた道を
命の胎が照らし出す道を
歩む
時を潜り
未来を切り開く
無数の命をゆっくりと孵化させる声が
樹と風とこども 原 和子
樹は わたしの
最初の恋びと
逞しい腕に
ぶら下がって遊んだ
裸足になって
むしゃぶりついていった
滑りそうになると
ザラザラした掌が
いつも しっかりと支えてくれた
上の枝をつかんで
ずんずん登れるようになった
ある日
不思議な衝動にかられ
わたしは 両脚で
かたく 幹を挟んで
耳を押しあてて
樹の
奥深い秘密の音を聴いた
くすぐられるような歓びに満たされ
上へ 上へと登っていった
「ここまで」と樹が言ったので
その枝に 腰かけてやすんだ
巻きついたかと思うと
怒ったように 振りほどいて
風も ここではぜんぜん違っていた
陽の光と一体となって
艶やかに 誘うように
逃げていく
樹に抱かれて
揺れながら
そのとき
はっきりと分かった
わたしとおんなじように
風も樹が 大好きだってことが
魔法 中島(あたるしま)省吾
いつかウォンが掘り出される
いつかドルがやってくる
いつかマルクの雨に遇う
いつか元がドアが閉まる前に駆け込み乗車で君の側に飛び込んでくる
いつか宝の山でお昼寝をして
いつか宝石の中でぐるぐる遊んでいる
「飽きたよ」
お菓子の家に入って
徳川家康に片思いされて、告白される
いつか宝石の街が君のものになる
いつか宝石商人が「忘れ物しましたよ」
と、君のポケットに世界最高と言われているクレオパトラのネックレスを押し込めて行く
いつか君の世界に勝手に宝石が勝手にやって来て、向こうから勝手にしつこく付きまとい宝石が君から
離れなくなる
「君しかいない」宝石が嫉妬して、君のことばっかり想って
君の側から宝石が離れない
いつからか君は宝の山に追いかけられる
いつからか君の隣には宝石が
君のことばっかり優先して、君から離れない
坂本龍馬と徳川家康と豊臣も織田も西郷も源も君のことを「だから。君のことを命をかけて守りたいか
ら。君のこと男として守りたいから。いや。俺こそ。俺こそ」
と、君のためにみんな必死に争う
君を守る運命の男は俺だと
つまり。I Love Youと告白される
「えー? 超ウザー。どの男にしようかなぁー」
君が言う
空の箱 瑞木よう
波をかぶった 空の箱
たぎる水蒸気に しめつけられて
爆音とともに 口を開けた
開けた口からは 厄災が
空に 溶けだし
雲になり 雨となって 降り注いだ
風に洗われて 光線を流し
変異を 呼び覚ましていく
パンドラの箱
嘆きの日を歌う男の声
息と声がまじり合い
柔らかく 空に響く
男の歌う その嘆き
深い陰りになって
心に積もる
光をぬぐって 土に埋める
見えない光を放つ 種が
枯れるのを 待ちながら
浮かぶ 晴 静
濃緑葉色の小枝揺れ
漆黒羽色の鳥一羽
一点凝視の狙う先
人影見えぬ自転車一台
前かごいっぱい
はち切れそうな買い物袋
ツン ツン ツン
辺りを窺い 右 左
ツン ツン ツン
辺りを窺い 右 左
ツン ツン ツン
辺りの気配冷静に
窺い 窺い 右 左
噂にたがわず賢い黒鳥
買い物袋のその中は
今日の夕餉の質素な惣菜?
囲む食卓子供の顔が
ツン ツン ツンつつくカラスに
大きく口開けかぁさん待つ子の顔が
身動きせぬよう物音させぬよう
追っ払えずに
じーっと見入ってしまった
世界 ハラキン
茎と花だけの彼岸花が
枯山水を侵食して
ひょろひょろと覆いつくした
上品な古典音楽が
咆哮のフリージャズに荘厳され
鼻の骨を折った
歩く人とその影は反転し
影が主人公になって
人は影に付き従った
はるか上空
小指のように見えた旅客機は
小指のような大きさで
空港に着いた
アリのような大きさの
人間たちが降りてきた
人生は一度きりではないという
事実が
事実としてやっと教科書に載った
きのうの世界は
水平線と垂直線だけだったが
きょうの世界は
曲線がはびこっている
剛毛を生やしたやつだの
体液をしたたらせたやつだの
きょうからきのうへと
不純な曲線どもが
水平線に手をだし
垂直線に足をからめて
抽象の絶叫のなかを
まさに侵食しつつある
連鎖 ハラキン
理科室の
静かな筋肉標本から
連鎖ははじまった
標本の右膝の靭帯が腐ってしまった
右膝をかばい続けたために
幾何堂の正方形は
左辺に負荷がかかり過ぎて
ついに疲労骨折した
杖を曳く生活に倦んで
男は動物をやめて植物になった
病葉だらけの楓になった
病葉はまさに病的な紅葉となって
名高い枯山水に
ワルツの速度で舞い落ちた
白砂は病をうつされたので
弱った白砂につけこんで
雑草がはびこった
女はそのハルジオンの可憐な花を愛で
ハルジオンになりきって
止揚のあげく発狂した
精神病棟では
いまこそ病という病を追放し
生老病死を生老死
にしようではないか
というシュプレヒコールが
伝染病のように
はびこりひろがった
かくして連鎖は終わらず
世界はなにひとつ治らず
世界像の真うしろで
化仏は暴悪大笑した
その憎憎しいメッセージを
生物室の
非情な骨格標本が
拝聴することをもって
連鎖は休戦となる
生の否定 ハラキン
鉱物の内奥でなにかが微かな音を立てたとき、鉱物は生物になりはてた。だけど足は生えなかったので、ぶざまに転がりながら 生きていった。コップの水に異常な光が差し込んだとき、水は生物になってしまった。たえず自らのからだに溺れてしまい、息が出来ず死にそうになる。密室の空気が風もないのにそよいだとき、空気は生物にされていた。誰もドアを開けないので、ずっと密室に閉じ込められながら、息をひそめていた。闇と真空に鎮まる、あいつをいのちにしてやろうという 意志のようなものが、前回は、土器に盛られたりんごや梨やぶどうの類を、すなわち静物を動物にしたり、鉄道のホームの下にはびこる植物を動物にして、けっきょく、しあわせになれなかった彼らは自死を選んだが、今回は、無機物を有機物と化する試みだった。いのちを得ていのちを謳歌すると思われたが、鉱物もコップの水も密室の空気も、唐突に押しつけられたいのちにとまどい、いのちの苦しいありように苦しみ、こんないのちは要らない、元の様態に戻してくれと、闇と真空に鎮まる意志のようなものに訴えた。このようにして、あまねく生というものは否定され、遠い昔、生の否定という神話になり、以来五千年間ひそひそと語り継がれた。
キツネの嫁入り 藤原節子
お日さまが照っているのに
雨が降っている
天は陽気にふるまっていても
心に涙を流している
平和な暮らしに酔っている時
いきなり襲ってくる厄災
人の顔の裏表と
運命の激変
戸惑いつつ
通り雨の中に
浮かびあがるのは
白無垢衣装のキツネの花嫁行列
父の言葉 根本昌幸
父が健在な頃
父は私によく言ったものだ。
持っている力は
十五分に出せ と。
十分にとは言わなかった。
十二分にとも言わなかった。
それが何を意味するものなのか
その頃 私にはよく分からなかった。
父がもうこの世を去って
久しくなる。
その言葉が
今
私には少し分かるような気がする。
この年齢になって
大震災があって
原発事故があって
私たちは古里を追われ
異郷の地で暮らしている。
―お父さん。
天上にいるお父さん。
私は十五分に力を出し切っています。
これ以上は出せません。
そこから見守ってください。
もう少し頑張ってみます。
ボンヤリ 加納由将
自分から
体が
離れていく
気が付くとベッドの上
腕から延びる
管は
一滴一滴
流れ込んでくる
いつからだったか
忘れていく
時間はのっぺり
溶け始め
モルタルの壁に
変わって
自分のリズムを
無くしていく
天井を
睨みつけている間も
輸液は流れ込み
枕元に
座っている自分をみつける
草青む 佐古祐二
土手の草には
眼がある
まぶしい光のなか
青い空を見上げている
高空では
雲雀が鳴き
その舌にも
春の光が宿っているだろう
真白な
はぐれ雲はゆるやかに
今
頭上を流れてゆき
吹き来る風に
草たちは
少女の髪となって
波打っている
古里 木村孝夫
あなたは
夏草のような匂いがする
と その女は言った
五年以上も前のことだ
私の好きな小説の中の
言葉だ
そう厚くもなく
飾りもない一冊の本なのだが
夏になると
文章の周りに草が生い茂り
好きな一節が
背伸びしないと
見えなくなってしまったり
ときどき海風が
ページを捲ったりするから
とんでもない場所に
連れて行かれたりしたが
それでも古里を
夏草に譬えて文章にした
この小説は好きだった
原発事故が起こってから
あの本は
行方をくらませていた
探すことも無く
ほおっておいたのだが
三回目の夏を迎えた頃
どこからともなくでてきた
本が言うには
暑い夏を新しく製本し
好きだった言葉を探して
付け加えたのだというが
文章を覆っているのは
ますます草ばかりではないか
根っこが家を傾ける太さになって
居座っているから
ガラガラと
家が崩壊し始めている
大分長い留守をした
もう家の歴史は
どうにもならなくなってしまった
あなたは
夏草のような匂いがする
そんな名せりふを
夏草の上で
耳打ちでもいいから
もう一度聴いてみたい
言葉をかむことも無く
言えるのだろうか
小説の中の文章は
夏になれば夏草に隠れ
秋になれば秋草に隠れる
季節は違っても
そんなせりふは
もう夢なのかも知れない
だから 一冊の本の中から
好きな言葉を
探し続けている
できるだけ多く
古里の言葉の匂いの中に
ごろりと
横になれることを夢見ながら
天地と裸身 葉陶紅子
息すたび 浮き沈みする乳房を
手に握りしむ 熱き宵なり
細長き 汚れし指に巻く風の
甘く匂える もの憂き宵は
香をのこし 冷めゆく肌をいとおしみ
弾ねる乳房に 唇あてぬ
かたち好く襟頸のばし 空色の
花見る空に ひと日は終わる
わが生まれ生きてある日を 人知らず
そを寂しまず 微笑める宵
天地(あめ つち)にわれひとり居の 安らけき
耳目口とも 棄て去りし後
この裸身生きてある日は われ死せず
そを悦びて 明日も生きめや
ピグマリオン あるいは 導きの女(チチェローネ) 葉陶紅子
寛衣脱ぎ 白き乳房と下腹部を
月に晒せば 蔦は絡まる
四肢捥ぎしトルソの頚に 愛しげに
腕巻きつける 裸体の女
乳房手に吸わせんとすも 顔失くし
誰と知られず 独り彳つトルソ
寛衣被り顔を覆いし 裸体の女
陰毛ありて トルソたりえず
裸女の肌 柔く匂える温もりと
月の滴で 傷は癒えるや
裸女達の 仕草/彳ち位置/目なざしを
読み解く者は 世界を征す
昼空に星を見る 眸(め)を育めば
顔両手足 傷より芽吹く
鷺 牛島富美二
いつもの散策路
坂道の傍らに
広い用水池があり
ふいに翔び出したのは
いつもは見かけない一羽の鷺
閘門(こう もん)の縁に止まると
私を無視したまま一点を凝視する
視線の先は池の水面
私は池に泳ぐ数羽の水鳥を見るだけ
鷺は不動のまま時を飲み込む
だからそれは彫刻の姿となり
水鳥も小禽も恐がらない
私も刻を胸に蔵しながら
ふっと彫刻に畏怖を覚える
こうしてじっとひたすら
一点を見つめて待ち続ける
これがああ 鷺の生きるということ
私はこれまで一点を見つめて
じっとひたすら待ち続けたろうか
じっと待たないために掌から
こぼれこぼれたものをつなぎあわせて
それを生きることだとしてきたのだろうか
母の小言を繰り返し咀嚼して
了解の域にたどり着くまでじっと耐えたろうか
若き日の恋文に記した言葉は
じっと待つ心の動きを記したろうか
その時彫刻は一閃して白い線となり
水上に漣を散らした刹那
嘴に冬の小魚が祀られ
鷺は再び閘門の縁に戻っている
あまりに鮮烈な光景に
私は生きることの意味を忘却して
こぼれこぼれているものに張り付かれ
私そのものが彫刻となり
黄昏の雪混じる寒風に
初めてじっと佇んでいた
コップ 左子真由美
その形が
うつくしいのは
かろうじて
薄い一枚の仕切りだけで
なかにつまっている水を
しっかりと
抱き留めているからなのだろう
倒れることなく
壊れることなく
まして
役目を捨て去ることなど
決してなく
水の重みを
支えているからなのだろう
みずからの
位置にあって
ひとつの任務を
なし遂げようとする
その決意の固さは
強い圧力で迫る
水ですら破れないほど
したたかで
静かである
うつり薫(か) 本多清子
車椅子に乗って
ぐったりしていた
舞台化粧のままの あなたは
強く抱きしめてくださった
わたしの着ていたレインコートが
さわ さわ 音をたてた
美しい瞳を
少しだけ見つめ
眼をうるませる
力だけしか なかった
再び 包み込むような
優しい 抱擁
かすかに 木犀の薫りがした
あなたは だまって
小さな紙切れを渡された
うつり薫といっしょに
それは
天国行きのキップであろうか
けれど まだ
幕は おりていない
窓ガラス 吉田定一
ガラスが 放射状に
ひび割れている
ガラス窓に走った
いなずまの 光のような
いい争ったおんなの悲鳴が
張り付いている
――す ま な い ね
かなしみの窓ガラスに
人差し指で しあわせの文字を書く
ほっと 熱い息を吹きかけ
冷たいガラスに 口づけする
ひび割れを 吸い取るように
唇で ふき取るように
(ああ、ガラス窓の安堵の涙か…)
沈黙の悲鳴が 雫となって
すっとガラスの頬に 流れ落ちる
算数の勉強
―『塵劫記』(吉田光由)に想を得て― 斉藤明典
数の勉強をしましょう
では声を合わせて
一・十・百・千・万 つぎは
億 十を八回かけます すなわち十の八乗
ここで囲碁の劫にはまって ちょっと道草
一劫は四億三千二百万年
法蔵菩薩が五劫もの間修業して
悟りを開き
阿弥陀仏になったという時間です
兆・京 京は十の十六乗
劫の一億倍は億劫
みなさん おっくうがらずに先へ進みましょう
垓・𥝱・穣・澗・正・載
さあ やってきました じごーくごくらく
極 十の四十八乗です そして
恒河沙 ガンジス河の砂つぶもこれくらい
阿僧祇 数え切れませんね その上は
那由他 きわめて大きな数 のあとは
不可思議 ふしぎの世界は十の六十四乗
無限大となり その先は 無限小へ
分・厘・毛 そして 糸は十のマイナス四乗
忽・微・繊 ついで 沙は十のマイナス八乗
塵 空中にただようチリ 十のマイナス九乗
埃 さらに小さなほこり 十のマイナス十乗
バイキンくんは 十のマイナス六乗メートル
ヴィールスくんは十のマイナス九乗メートル
オングストロームに研究の名を残した
スウェーデンの物理学者
まだまだ
渺・獏 バクゼンとして 十のマイナス十二乗
ここまで来ると あいまいもこもこ
模糊 ぼんやりしてはっきりしない
十のマイナス十三乗
よくできました お疲れさま
関ヶ原の戦いまで 清沢桂太郎
一五八二年 本能寺の変 織田信長死ぬ
関ヶ原の戦いまで十八年
一五八七年 豊臣秀吉九州を平定
一五九〇年 小田原征伐 秀吉全国統一
関ヶ原の戦いまで十年
一五九一年 千利休切腹
関ヶ原の戦いまで九年
一五九二年 秀吉朝鮮出兵
一五九三年 秀頼誕生
一五九五年 秀次切腹
一五九七年 秀吉再び朝鮮出兵
関ヶ原の戦いまで三年
一五九八年 秀吉死ぬ
関ヶ原の戦いまで二年
一六〇〇年十月二十一日(慶長五年九月十五日)
関ヶ原の戦い
余りにも短い天下人豊臣秀吉の世
余りにも激しい時代の変動
大名や足軽は何を思い
どう生きようとしたのだろうか
農民 漁民 商人は何を思い
どう生きようとしたのだろうか
私は?
ホームに住んで 神田好能
ホームに住んで幸せ
姉さんや妹が居るみたい
みんな顔を合わすと
にっこり してくれる
お互いに「今日は元気かな」
って想いやるような
やさしい目をしてる
老人になるとみんな
やさしくなる
嬉しいなあ
天狗さんの顔 田村照視
昼間からそんな赤い顔して
どないしはったんどす
お酒は飲んだはらしまへんわなあ
臭いがしまへんわ
ごつい鼻の先が
ぴくんぴくん くるんくるん
よう動いてますなあ
あんたはんは表情(か お)には出てへん
そう思うたはりますけど
こっちから見たらよう分かりまっせ
恐い顔したはりますけど
お喋りはおとなしおすなあ
もの凄う丁寧ですわ
まるで国会答弁の政治家みたいや
いろんな世界に
よう似た人ぎょうさん居たはりますな
天狗さんは空を飛び回ったはるし
上から見たら庶民の動きが
よう分かりまっしゃろ
そやけど空からやったら遠すぎて
お人さんが蟻に見えるんと違いますか
あんたはんには愚鈍な生きものに見えまっしゃろ
けど蟻さんは賢い生きものでっせ
ひょっとしたら知識も教養も才能も
あんたはんより上かも
いっぺんよう考えてみはりますか
(自戒をも含め)
戦友の死 田村照視
師走の風が吹くと
遠い思い出に胸が痛くなる
三十五年にもなるが
未だに気がめいってくる
あの日は経理課長と
お歳暮贈りの百貨店へ
気ぜわしい喧騒とジングルベルが
やたらボリュームを上げて流れ
街にはゆき雲が低く垂れこめ
木枯らしは
大通りに枯葉の渦をつくり
吹き抜けていた
突然の訃報は事務局からだった
あいつも業界では
若手の流通委員
業界発展のため共に
企業戦士として
将来を嘱望されていた
脳天をハンマーで
殴られる衝撃
いったい何があったのだ
いつも陽気で積極的なあいつ
自死と聞かされても
すぐには信じられない
遺書は長男と専務へ
奥さんには長文であったらしい
保険金は銀行への返済と
遅滞している取引先への支払い
こまごまと書かれていたという
遺書を書いていたあいつの心中は
どうしても計り知れない
どんな表情で書いていたのか
どうしても想像できない
世はまさに
右肩上がりの景気がつづき
週に二度や三度は
祇園や木屋町に繰り出し
酔いしれて
無邪気に騒いで梯子酒を
世間体を気にしてか
だれにも弱みを見せずに
いつもにこやかで
いきづまった素振りは
微塵も見せなかった
生きていれば
なんとかなったはず
頭の中には保険金だけしか
浮かばなかったのか
ひと言の相談もなく
逝ってしまった
無念のなか
四十代の半ばにして
事業に命をかけた男の生き様を
思い知らされた
ねこやなぎの花 蔭山辰子
冬の間かぶっていた茶色の帽子をぬいで
手ざわりの快いビロードの白い芽が出てくる
私は これがねこやなぎの花だと思っていた
ところが
見るみるふくらみ
その白い綿帽子に
いっせいに 細かい黄色の小花が咲いた
腰を病んだ辛い冬
茶の間の花瓶に
ただ一つねこやなぎに春の息吹を発見
でも まだ
帽子を脱げない子がいくつか
がんばれ
たつこも がんばる
食べる 弘津 亨
アイスランド産赤魚
北の冷たい海
灰色をした島影
きみを捕らえた網が引き上げられる
加工工場で
ふるさとの海の記憶は
鱗や内臓とともにそぎ落とされ
切り身にされると
きみは商品として
買い物籠の中へ
食卓を囲み
甘からく煮付けたきみをくちに含む
きみの生きた時間
きみの眼が見た
ゆれる水のカーテンにうつる太陽 いっぴきの雌と
鰭を触れ合わせて愛しあった記憶
は いまどこの海を泳いでいるか
いのちがいのちを食べる
という 血の色をしたいとなみを
この文明は忘れさせる
箸がとまる
食卓のはるか遠くで
海は
荒れている
真っ青な空 関 中子
夜になっても空
ここに底がないという空
どこかに底があると思う
ここに空
わたしには終りがまだ来ない
空を寄せゆっくり起き
ぐずぐず眠り
そろそろ食べ
うろうろ歩く
ここのこの空の下をわたしのところにしよう
ここのこの空の下にいるものは青くなるだろう
わたしの吐息にはわたしという言葉のひかりが蛍火のように点滅し
そのひかりは
青く思える
わたしの眼はこの空の下にたまった水をわたしの身体からかいだし
青いしずくを飛び火のように
椿の樹に散らす
がらんどうの幹は髪をたらし
節々のきしみを音楽にしよう
野で横になろうが
他樹にもたれようが
川にいようが
砂にうもれようが
椿の香にみち青にしみるわたし
このわたしの身を溶きだれかを青くしよう